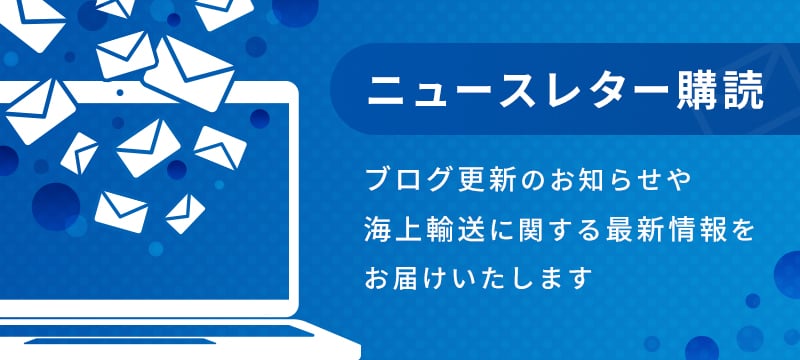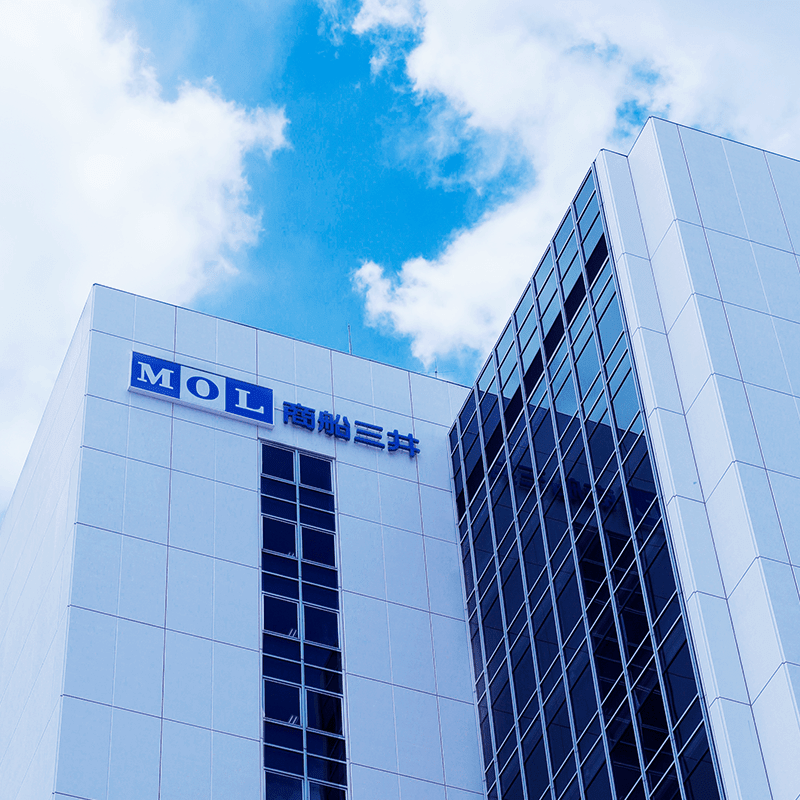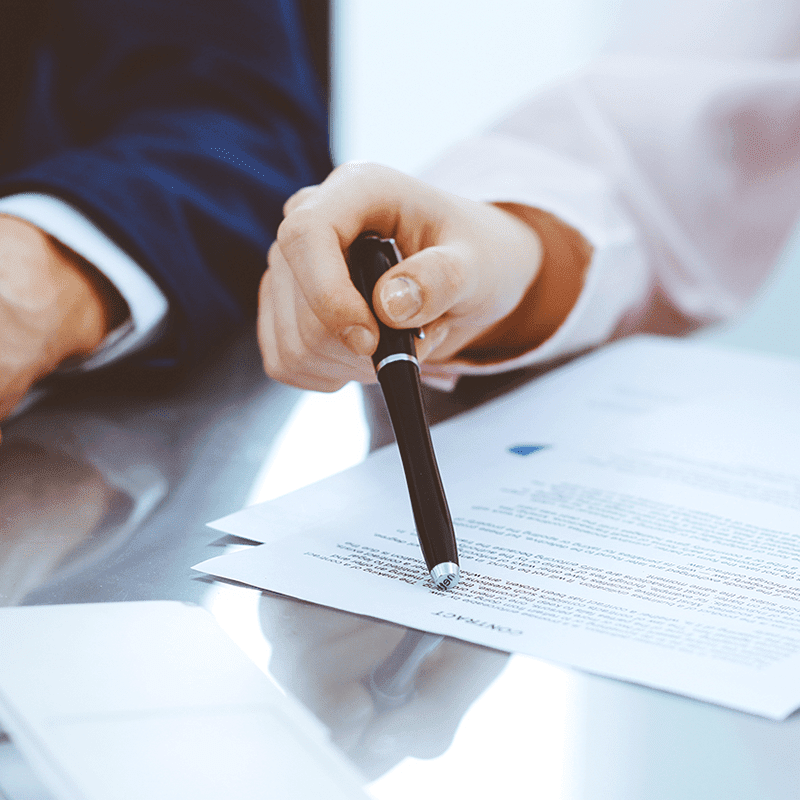BLOG ブログ
海に浮かぶ“白い卵”──水素旅客船「HANARIA」誕生!
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年09月08日
2024年3月、関門海峡に誕生したのは、日本初の水素燃料旅客船「HANARIA(ハナリア)」。温室効果ガスを一切排出せず、驚くほど静かで美しいこの船は、脱炭素社会の象徴として多くの注目を集めています。
乗り心地、航続性能、安全性、そして未来の可能性─あらゆる面で革新をもたらすHANARIAは、まさに“海の常識”を塗り替える存在です。その開発から運航に至るまでには、数々の課題と挑戦がありました。本記事では、HANARIAの誕生に込められた想いや技術の裏側に迫ります。そして、記事の最後には実際に乗船した体験記もご紹介!ぜひ最後までお楽しみください。
 (HANARIA公式HPより)
(HANARIA公式HPより)
キーポイント
- 日本初の水素旅客船「HANARIA」が関門海峡に誕生
- 静音・ゼロ排出で快適な未来型クルーズ体験
- 3つの電源搭載のハイブリッド型電気推進船で安全性と持続性を両立
- 独創的な“白い卵”デザインが海に映える存在感
- 「シップ・オブ・ザ・イヤー」「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー」W受賞の革新船、脱炭素社会の象徴へ
水素で脱炭素社会を実現するために
今回の取材では、HANARIAの建造・実用化に深く関わった、商船三井テクノトレード株式会社 水素ビジネスデザイン部の以下の4名にお話を伺いました。
- • 部長 山川 雅弘 氏
• 専任部長 京田 繁樹 氏
• 部長代理 向山 敦 氏
• 主任 金子 岳太 氏
商船三井テクノトレードでは、再生可能エネルギー分野への本格的な事業展開を見据え、水素を活用した新たな海事ソリューションの可能性を模索。HANARIAは、その第一歩として構想されたものです。
向山
水素は、無色・無臭・無毒の気体で、アンモニアやメタノールに比べても安全性が高く、環境負荷も極めて小さい燃料です。液化水素は温度管理など扱いが大変ですが、水素ガスなら内航船の船員でも扱いやすい。水素を選んだのは、そうした総合的な実用性からです。最終的に、日本財団の『ゼロエミッション船プロジェクト』に採択され、本格的に建造へと進みました。
水素燃料船の実用化には、まだ確立されたモデルがなかったため、技術面でも制度面でも数々の新たな取り組みが必要でした。しかし、その先に広がる可能性を信じ、商船三井テクノトレードは勇気をもって一歩を踏み出しました。
 (HANARIA公式HPより)
(HANARIA公式HPより)
3つの電源を搭載し、安全と持続性を両立するパワーマネジメント
HANARIAは、水素燃料電池、リチウムイオンバッテリー、そしてバイオディーゼル発電機という3種類の電源を搭載したハイブリッド型電気推進船です。HANARIAには、複数の電源を柔軟に使い分けられる「パワーマネジメントシステム」が搭載されています。これは、3種類の電源をタッチパネルの操作で任意に選択でき、本船の出力変動に応じて電源の負荷配分を自動で調整できるシステムで、新たに開発された発電・推進機器と連携して制御されています。
船に搭載されている舶用水素燃料電池システムは、ヤンマーパワーテクノロジーが開発したもので、本船が初の導入事例です。水素燃料電池とリチウムイオンバッテリーによる「ゼロエミッションモード」での運航や水素燃料電池とリチウムイオンバッテリーにバイオディーゼル発電機を併用した「ハイブリッドモード」で運航することができます。リチウムイオンバッテリーは、水素燃料電池・バイオディーゼル発電機からの充電に加え、陸上の給電設備からも充電が可能です。また、HANARIAは国土交通省が定める「水素燃料電池船の安全ガイドライン」に初めて準拠した船舶でもあります。
 水素タンク(現地撮影)
水素タンク(現地撮影)
向山
ディーゼル燃料を使う従来船舶と比較すると、3つの電源を使用する場合では温室効果ガスの排出量を53%削減できます。ゼロエミッションモードでは言葉通り排出量“ゼロ”、つまり100%削減でき、最大で約5〜6時間の運航が可能です。しかし水素とバッテリーだけでは、まだ商用運航には不安がありました。水素燃料電池の実績は限られており、供給インフラにも課題が。そこで万が一に備え、実績のあるバイオディーゼル発電機を第三の電源として組み合わせました。商用ベースでの安定運航には“冗長性”が不可欠だったんです。
水素供給の新たな形を模索。運用には今後の課題も
HANARIAでは、トヨタ自動車の水素燃料車「MIRAI」に採用されている技術を応用し、船舶向けの大型ポータブル式水素タンクモジュールを新たに開発しました。本船には、2本の大型タンクを1ユニットとする脱着式モジュールを8基搭載しており、これは商用船舶としては日本初の試みです。このタンクは、積み下ろしのしやすさだけでなく、落下や衝突、被弾などのリスクにも耐えうる高い強度が確保されています。
京田
MIRAIが約5kgの水素を搭載するのに対し、HANARIAでは約150kgが必要ですから、MIRAIのタンク技術をそのまま使うことはできません。容量が桁違いに大きいため、減圧装置や減圧弁、モニタリングシステムなども新たに開発しました。
向山
こうした異業種のコラボレーションは珍しい取り組みです。船に搭載できる水素タンクの実現に向けて複数の企業と連携しながらシステムを実現しました。
3.jpg?width=2880&height=2160&name=%E5%94%90%E6%88%B8(%E6%A8%AA)3.jpg)
(現地撮影)
HANARIAでは、陸上の水素ステーションで専用タンクに水素を充填し、クレーン付きトラックで船まで輸送。船上で燃料として使用します。このシステムは、高圧ガス保安法や消防法、船舶安全法など、陸海両方の法規制に対応しています。設計段階から国土交通省や海上技術安全研究所の指導のもと、リスクシミュレーションや各種検証を重ね、安全性を確保しました。
山川
水素供給に関しては、港湾の固定インフラに依存せず、柔軟に陸上の水素供給設備を活用できるという利点があります。ただし、実際に使用可能な水素ステーションは限られており、現状では全国にある約150カ所のうち、自動車以外の充填が可能な場所は数カ所しかありません。経産省や内閣府とも連携し、対応可能なステーションの拡大に向けて働きかけを続けていますが、課題はまだ残っています。

(現地撮影)
海に浮かぶ“白い卵”。未来を感じさせるデザインと快適性
HANARIAのもうひとつの大きな魅力は、その独創的なデザインです。船体は流線型のトリマラン型をベースとし、上部構造はまるで海に浮かぶ卵のような滑らかなフォルムを描きます。
向山
まったく新しい船をつくるなら、デザインもこれまでにないものを。そう思って“海に浮かぶ卵”をイメージしました。船体の曲面加工には製造側も苦労したと聞いています。
船内は白を基調とした洗練された空間。100インチモニターや270度投影可能なプロジェクターを備え、可動式の座席を活用したイベント仕様、バリアフリー対応など、多様なニーズに応えられる設計にこだわりました。
金子
また、従来のディーゼル燃料船に比べ圧倒的に騒音・振動が少ないという特長があります。水素で航行しているときの静かさには、乗船された方も驚かれます。速さはそのままなのに、まるで止まっているかのような感覚を味わえたという感想もいただきました。
2024年4月からは一般向けのクルーズもスタートし、下関市の唐戸桟橋をはじめ、北九州市の門司港や小倉港で運航しています。海響館やゆめタワー、そして往来する大型船など、関門エリアの風光明媚な風景を堪能することができます。
 (現地撮影)
(現地撮影)
山川
揺れが少なく、静かで快適。テーブルの上にワイングラスを置いても倒れないほどです。2階のオープンデッキでは風を受けながらたいへん快適に過ごせたという声も多く、お客様の満足度は非常に高いです。乗り物酔いをしやすいけれど、この船なら安心という方もいらっしゃいます。
ある車いす利用の高齢者からは「人生で一番楽しい体験だった。」とまで言われたそう。ゼロエミッションは、環境だけでなく、人の心をも豊かにする技術なのです。
 (現地撮影)
(現地撮影)
山川
HANARIAは地元の皆さまに親しまれる存在となりつつあります。観光地域づくり法人である関門DMOの方から「HANARIAを目玉に、関門エリアの魅力をアピールしていきたい」という話もあり、まずはこの地域のアイコンのひとつになれればと考えています。
船の仕様や水素供給の関係で、異なるエリアでの展開にはさまざまなハードルがありますが、今後ニーズがあれば、神戸・大阪・東京・横浜など別の地域での展開も検討していきたいですね。
「シップ・オブ・ザ・イヤー」「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー」をW受賞
HANARIAは「シップ・オブ・ザ・イヤー2024」を受賞し、その後「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー2024」も受賞。両賞とも船舶業界では大変名誉ある賞であり、かつダブル受賞は史上初の快挙です。
向山
日本船舶海洋工学会が主催する「シップ・オブ・ザ・イヤー」は、毎年日本で建造された話題の船の中から、技術的・芸術的・社会的に優れた船に与えられるもの。船の“カー・オブ・ザ・イヤー”の様なものです。最初からエントリーを狙って検討していたわけではありませんが、技術面と芸術面、両方を評価されるという意味では、まさにHANARIAにぴったりの賞でした。
金子
「シップ・オブ・ザ・イヤー」受賞が決まったのは、ちょうどバリシップという海事分野のイベントでお客様とHANARIAに乗船していたとき。ご一緒していた業界の方々から、たくさんの祝福の言葉をいただきました。
「シップ・オブ・ザ・イヤー2024」「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー2024」は、いずれもHANARIAの建造や、水素サプライチェーンの構築をともに担った複数企業との共同受賞。かつてない規模の水素燃料船をつくるという困難な課題に対し、多くの企業が力を合わせて挑んだ取り組みが評価されたことは、これからの脱炭素社会の実現に向けて非常に意義深いものです。
 表彰式写真(商船三井テクノトレード提供)右から
表彰式写真(商船三井テクノトレード提供)右から
日本船舶海洋工学会 会長 鈴木 英之様、
商船三井テクノトレード株式会社 特別顧問 川越 美一、
商船三井テクノトレード株式会社 代表取締役社長執行役員 福島 正男、
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事 有働 隆登様、
本瓦造船株式会社 代表取締役社長 本瓦 誠様
水素ビジネスの未来に向け、HANARIAから広がる海の脱炭素化
HANARIAの成功は、単なる“技術のショーケース”では終わりません。水素社会の現実解として、次なる展開へと舵を切っています。
京田
ゼロエミッション船の実現は、脱炭素社会の推進と2050年のカーボンニュートラル達成に大きく貢献します。水素燃料電池とリチウムイオンバッテリーによる運航は、環境負荷を抑えるだけでなく、振動や騒音が少なく、無臭・無害の排気で船内も快適。乗客だけでなく船員の環境改善にもつながるなど多くのメリットがあります。
商船三井グループ全体としても、さまざまな次世代燃料を試行する中で、当社は“水素”の可能性に注力してきました。HANARIAのような水素船が、1隻、2隻と増えていけば、水素供給や関連機器の事業展開にも弾みがつく。HANARIAの経験と知見を活かして、新たな展開へ繋げるチャレンジをしていきたいと考えています。
HANARIAは、まさに“未来の船”を体現する存在です。脱炭素社会の象徴として、また心地よいクルーズ体験を届ける旅客船として、これからも多くの人々の心をつかんでいくでしょう。そしていつの日か、HANARIAの航跡が、世界の海に刻まれる水素船のスタンダードになる日が訪れるかもしれません。
実際にHANARIAに乗船してきました!
2025年8月、本サイトMOL Solutionsの運営事務局メンバーが、下関でHANARIAに乗船してきました!
今回体験したのは、唐戸桟橋発の「唐戸60分クルーズ」(料金:2,500円)。巌流島を海上から眺め、関門橋の下をくぐるという、関門エリアの魅力を満喫できるコースです。
唐戸桟橋に到着してまず目を引いたのは、HANARIAの独特なフォルム!まるで“白い卵”のような滑らかなデザインが、青い空と海に映えて、他の連絡船とは一線を画す存在感を放っていました。
4.jpg?width=751&height=563&name=%E5%94%90%E6%88%B8(%E8%88%B9%E9%A6%96%E5%81%B4)4.jpg) (現地撮影)
(現地撮影)
船内に入ると、1階は広々としていて高級感のある空間が広がっていました。大きな窓からは関門の風景がしっかり楽しめます。2階のオープンデッキにはゆったりとした椅子が並び、潮風を感じながら下関や門司の街並みを眺めることができます。
離岸後、「ゼロエミッションモードで航行を開始します」というアナウンスが流れた瞬間、エンジン音と振動が消え、船内が驚くほど静かに。まるで止まっているかのような感覚に包まれ、乗り物酔いしやすい筆者でも快適に過ごせる、優雅なクルーズ体験となりました。
 (左)関門海峡は1日に500~600隻、多い日には1,000隻近い船が行き交うだけあって、クルーズ中は多くの貨物船とすれ違いました。 (右)2階から見える巌流島。島のまわりをほぼ1周します。(現地撮影)
(左)関門海峡は1日に500~600隻、多い日には1,000隻近い船が行き交うだけあって、クルーズ中は多くの貨物船とすれ違いました。 (右)2階から見える巌流島。島のまわりをほぼ1周します。(現地撮影)
 船内から眺める関門大橋(現地撮影)
船内から眺める関門大橋(現地撮影)
そして、関門橋の真下を通過した直後には、なんと野生のイルカの群れと2回も遭遇!「右手にイルカがいます」と船長のアナウンスが入り、乗客全員が大興奮。思いがけないサプライズに、船内は大盛り上がりとなりました。
HANARIAは、「シップ・オブ・ザ・イヤー2024」と「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー2024」のダブル受賞を果たした注目の船。唯一無二の外観と、衝撃的な静けさを実際に体験し、その受賞にも深く納得しました。
北九州エリアにお立ち寄りの際は、ぜひHANARIAに乗船してみてください!環境にも人にもやさしい、未来の船旅が待っています。

HANARIA公式サイト
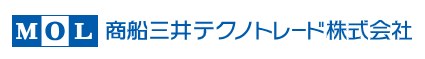
商船三井テクノトレード株式会社 公式サイト
オススメ記事
2021年03月10日
- エネルギー
2022年06月28日
- 海運全般
2021年04月13日
- 海運全般
2025年04月21日
- 海運全般
2020年09月02日
- 海運全般
最新記事
2026年01月26日
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年12月24日
- 海運全般
2025年12月15日
- 環境負荷低減
- 海運全般