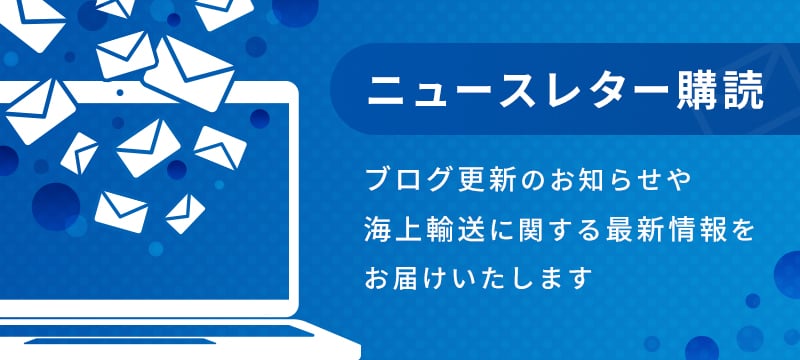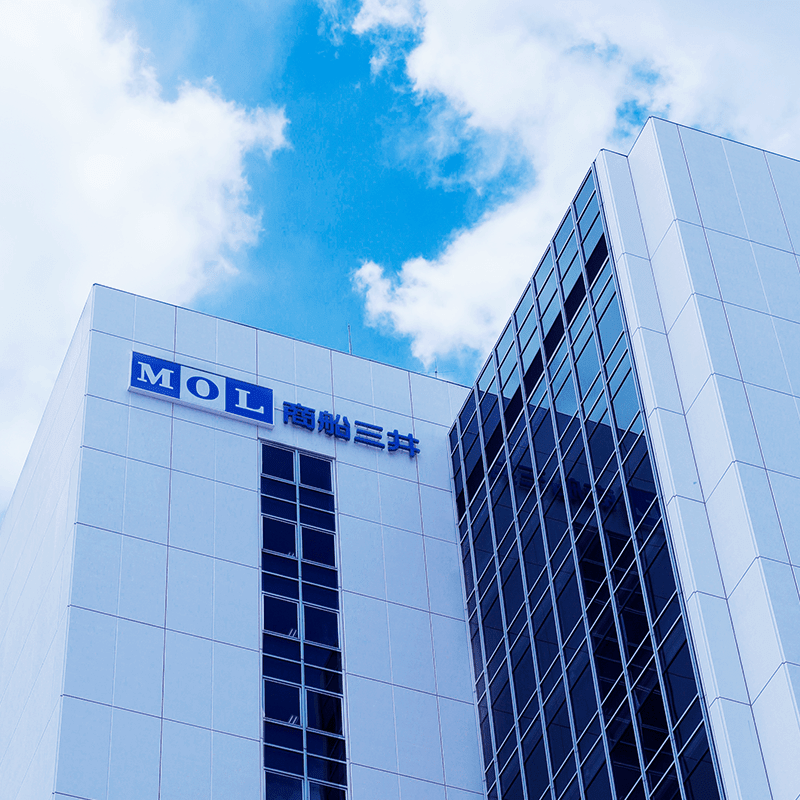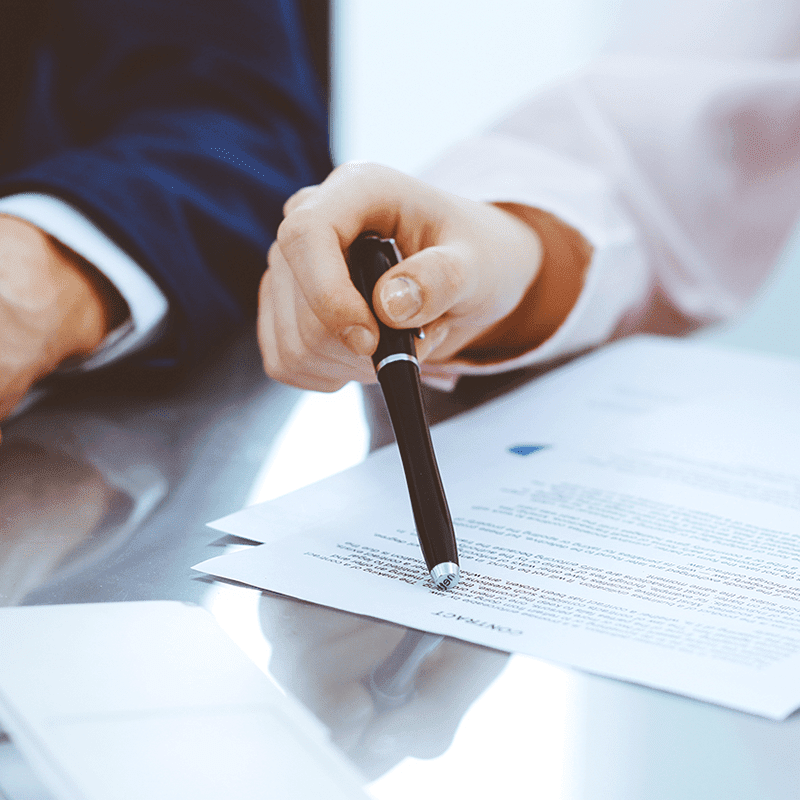BLOG ブログ
中国から見る自動車新時代~激動の中国自動車輸出ビジネス(後編)~
- 海運全般
2025年05月19日

今回のBlogは2023年の前編に続き、中国より現地駐在員の生の声をお届けいたします!
前回はこちら
だいぶ時間が経ってしまいましたが、今回の中国自動車Blogは前回お知らせした通り、中国自動車ビジネスの現状と輸出動向等に関して簡単にご紹介したいと思います。
(この記事は2025年3月に執筆されたものです。)
(右写真:上海静安寺、筆者撮影)
キーポイント
- 中国の自動車市場はEVを中心に急成長し、2024年には販売台数が3,140万台を突破
- 輸出台数も世界一となり、特にロシアや中東、EU向けが拡大
- 国内では競争が激化し、多くの新興メーカーが撤退する一方で、EV高級ブランドが台頭
- 自動運転技術も進展し、レベル4の無人タクシーが一部都市で実用化
- 地政学リスクや保護主義の影響を受けつつも、中国は輸出戦略を多様化し存在感を強めている
中国車の総販売台数
まず前回ご紹介した時点、2022年末での中国車の総販売台数は約2,700万台でしたが、2023年は3,009万台、2024年は3,140万台と、コロナ以降の回復傾向から一気に3,000万台の大台を突破しています。

(出典:MarkLines)
この好調ぶりには各種要因があるのですが、やはり自国自動車産業を肝の1つとして扱いたい政府による各種補助金等制度が購入・買い替え等を促し、それに合わせて各メーカーもEVを中心とした新車をどんどん発表したこと、および自動車輸出に対しても積極的に力を入れていたことが主な理由として挙げられると思います。
ちなみにメーカーごとの2024年売上ランキングは以下の通りです。前回のブログに載せた2022年のランキングと比べて頂くと、2年の間に台数規模も順位も大きく様変わりしていることが分かります。
.png?width=636&height=437&name=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%B0%E6%95%B0_%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0(2024%E5%B9%B4).png) (商船三井調べ、合弁・輸出台数含む、単位:万台)
(商船三井調べ、合弁・輸出台数含む、単位:万台)
2023年頭には日本にも進出したBYDですが、とうとう2024年には長らく販売首位であった上海汽車を抜きました。データによれば、モデル別の販売台数TOP10のうち6モデル、新エネルギー車(NEV)に限ればTOP10のうち9モデルを占めていることが明らかにされています。
中国車の海外輸出
2022年、中国からの自動車輸出台数は311万台でした。しかしながら2023年に491万台と日本を抜いて世界一の座につき、さらに2024年は586万台(641万台という説も)、更なる飛躍をみせています。
先ほどご説明した通り、中国政府は自動車産業に重きを置く中で、その一手段として自国製自動車の海外輸出に力を入れています。最近はEVからHEV(Hybrid Electric Vehicle/ハイブリッド自動車)への回帰の流れなども一部で見られたりしますが、それでもなお、中国としてはEV含めたNEV(New Energy Vehicle)を自動運転、Connected技術などと合わせ、自国技術の集大成として海外へと販売する、という大きな方向性自体は変わらないものと思います。
.jpg?width=751&height=452&name=%E6%97%A5%E4%B8%AD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%8F%B0%E6%95%B0(%E4%B8%87%E5%8F%B0).jpg)
(出典:MarkLines他。2024年586万台ベース。KD(組立用パーツ)等輸出含む)
また、中国発の輸出国別で見たデータが以下の通りです。変遷が分かりやすいように、輸出台数が急激に増え始めた2021年(総輸出約200万台)との比較を載せていますが、台数の増加幅、絶対値共にロシア向けの出荷が群を抜いています。現状のロシア・ウクライナ問題が発生したのち、日本や欧米の自動車メーカーはロシア市場から退出しましたが、その代わりに中国メーカーが一斉に進出し、そのシェアを伸ばしています。
その他、以前から中国メーカーがシェア拡大の種まきをしていた中東地域や、現状関税問題で踊り場に差し掛かっているもののEV輸出の重点地域であるEU向けが大きく伸びていることが分かります。
私は自動車船部の所属としてこのブログを書いていますが、輸出の方法は自動車船だけに限られず、コンテナ船やバラ積み船もありますし、ロシアや中央アジア向けは列車やトラックがほとんどを占めています。事実、TOP10以下の10万台前後の輸出国にはカザフスタンやベラルーシなど、中央アジアの国が顔を並べています。
.jpg?width=751&height=451&name=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%85%88%E5%9B%BD%E5%88%A5%E5%8F%B0%E6%95%B0(TOP10%E3%80%81%E4%B8%87%E5%8F%B0).jpg)
(中国各種データより商船三井調べ。KD(組立用パーツ) 等輸出含む)

中国最大の自動車輸出港の1つである上海海通港の自動車蔵置場(これでも一部)
これまでの輸出拡大に関連する数字のラストとして、輸出台数におけるICE(ガソリン車)とNEVの割合を示したものを掲載します。
まず1つ目のグラフは国内の自動車販売の数字です。最初にお示ししたグラフと似ていますが、輸出分が引かれたうえ、ICEとNEVに分かれています。そして2つ目のグラフは輸出台数だけ切り出してICEとNEVを分けたものとなっています。
これを見ると、中国国内販売におけるNEVの販売台数はすさまじいスピードで伸びているのに対して、輸出に関してはそこまでではなく、ICEがまだまだ太宗であることが分かります。もちろん、129万台もNEVを輸出しているということ自体が絶対値としては大きいのですが、中国国内において政策的に売りにくくなったICEを海外に展開しているという見方もできるのかもしれません(後述)。
特に中国製EV輸入に関する障壁が上がりつつある昨今、2025年はこのグラフがどのような形を示すのかに興味が持たれるところです。
.jpg?width=881&height=529&name=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%86%85%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%B0%E6%95%B0(%E4%B8%87%E5%8F%B0).jpg)
.jpg?width=881&height=603&name=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%BC%B8%E5%87%BAICE%20NEV%E5%89%B2%E5%90%88(%E4%B8%87%E5%8F%B0).jpg)

上海港から自動車を輸出すべく積み込みに勤しむ弊社運航船Dugong Ace(筆者撮影)
中国自動車業界と輸出の今後
先ほど書きました通り、不動産等の不況等で苦しい経済状況が続く中、中国が自動車産業を頼みの綱の一つとして重視し続けることは間違いないと思います。それを受けての販売3,000万台(総数)、輸出580万台ではありますが、同時に様々な不安要素も存在しています。そのうちの一部を簡単にご紹介いたします。
①中国国内の不景気
ニュース等で報道されている通り、中国の不動産成長は過去のものとなり、現在は多くの不動産会社が厳しい状況に陥っています。以前は不動産の高騰で多くのお金を得て、それでよりよい家や車を買っている人が相当数いましたが、そのサイクルが終わり、購買意欲にブレーキがかかっています。
また、一般の層に関しても、コロナによる小売りを中心にした産業へのダメージ等あり、若年層を中心に失業率が高くなっています(発表によれば、中国の失業率は全体では5%程度。日本は2.5%前後。一方若年層はコロナ後に20%超。現在は15%あまり)。
②競争過多
上記のような不景気もあり、各社はそのような状況下でも売れるような安価な車を販売し、かつ政府も補助金等で買い支えを行いました。そして数多くの新規参入メーカーも現れた中で、現在中国国内の自動車販売競争は非常に熾烈なものとなり、研究費がかさむのに対して利益率はかなり厳しくなりがちで、多くの新規参入者が退場しています。破産後も再編や再生手続きを行っている会社もあるのでここでは列挙はしませんが、メディアによれば既に400社以上が倒産や撤退をしたとの報道もあります。
同時に伝統メーカーであっても、その順位変動が非常に激しくなりました。以下の図は2022年と2024年の販売台数の比較ですが、中国メーカー、日本メーカー、欧米メーカー問わず、この2-3年で大きな変動が起こっていることが一目でわかります。
今後もこのような競合・淘汰は厳しくなっていくという意見が多く、最後に生き残るのは5社程度だとする論調もあります。.jpg?width=987&height=591&name=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%B0%E6%95%B0%E6%AF%94%E8%BC%83(2022vs2024).jpg)
(出典:MarkLines)
また、高級車ラインに関しても、過去はBBA(ベンツ・BMW・Audi)やLexus、ポルシェなどを買うことが成功者のステータスとして重視されてきましたが、中国のEVやIT技術の進歩に伴い、各メーカーがスタイリッシュで機能性豊かな高級車ラインを販売するようになり、これらが伝統高級車の一部のシェアを奪うことによって、そういったブランドの輸入にとっても厳しい状況が発生しているという事実もあります。
.jpg?width=773&height=484&name=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%8F%B0%E6%95%B0%20(1).jpg)
(商船三井調べ)
余談ですが、近年発売された中国発高級ブランドの中で、注目の1つであるAITO(問界)。これは、Seresという中国メーカーと、かの有名なファーウェイ傘下のHIMA(Harmony Intelligent Mobility Alliance)というブランドがタッグを組み完成させた1台です。そのセンサーや高性能のオペレーティングシステム、スマホとの連結性などに定評があり、2024年には中国国内で44万台を売り上げました。
 街中のショップで携帯電話と同じように売られる問界(筆者撮影)
街中のショップで携帯電話と同じように売られる問界(筆者撮影)
.jpg?width=570&height=358&name=%E8%A1%97%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%A7%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%A3%B2%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%95%8F%E7%95%8C(2).jpg)
(筆者撮影)
HIMAはAITOのみならず奇瑞汽車とのLuxeed(智界)、北京汽車とのStelato(享界)、江淮汽車とのMaextro(尊界)、上海汽車との尚界など、多くのコラボレーションを進めており、Maextroについては初モデルの販売価格が2,000万円を予定するとして話題になっています。
③貿易戦争
EUへの多くのEV流入による保護主義の勃発や、トランプ大統領による関税戦争などは、自動車の輸出を進めていきたい中国にとっては頭の痛い問題です。
EV以外の車種輸出の拡大(前述、国内で競争力のないICEを海外へ?)、欧米・日韓系メーカーが撤退したロシアなど、欧米以外の第三国への輸出拡大、第三国への工場建設による出荷地変更など、様々な策が取られていますが、例えばロシア・ウクライナ情勢が改善したらどうなるか、第三国に工場を建設したらただでさえ不景気な中国国内の雇用はどうなるか、など問題は単純ではなく、政府・メーカーも難しいかじ取りを求められる場面が出てくるものと思います。
このように、現状の中国自動車業界を取り巻く環境につき、基本的な部分を数値と共にご紹介してきました。しかしながら各所で書きました通り、この環境の変化は非常に早く、また2-3年もすればここで私が書いたことも過去のものとなり、全く違った世界が広がっているものと思います。日本にはBYDが大々的に進出してきましたが、まだまだ中国メーカーのシェアは低く、今のところ日常生活で中国車のことを感じる機会は少ないかもしれません。しかし、世界における中国車のシェアは徐々に高まっているのが事実です。最近はネットニュースなどでも中国車についての記事が報じられることも出てきていますので、たまにはどんな車があるのかなと目を向けてみるのも新鮮でいいかもしれません。
我々商船三井としましては、国内販売・海外販売、輸出・輸入にかかわらず、このような変化の流れにしなやかに対応し、より良いサービスをお客様に提供していけるよう、引続き情報把握に努め、サービス品質向上を行ってまいります。
あとがき(中国の車事情小ネタ2)
①自動運転
中国がITやAI技術に力を入れていることは前編でも書きましたし、最近のDeepSeekなどの話題でもよく取り上げられるところです。そんな中、自動車に関係するところとしては自動運転が1つの良い例かと思います。
中国ではいくつかの都市に実験区域を作り、その区域の中で自動運転の試験を行っています。主には自動運転タクシーを運営し、情報を収集しています。私も百度(Baidu)が運営するApollo Goと、Toyotaが出資することでも知られているPony.aiの2種類を北京と重慶の試験区で試してきました。
まず彼らの自動運転レベルはレベル4。下の図によれば条件下での完全自動運転。有人車両と無人車両があり、Ponyでは運よく無人車両に乗れました。
.jpg?width=780&height=456&name=%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%88%86%E3%81%91%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%9B%B3%20(3).jpg)
(自動運転レベル分けイメージ図)
乗った感想としてはまあまあスリリング。意外とスピードは出しますし(一部地域の人にとってはそれでも遅い、という評価があるようですが…)、安全第一なのでちょっとした他車の挙動でがくんと急ブレーキをしたり。試験区自体もそこまでゴミゴミしていないところなので、これが上海などの街中で他の車と一緒に走れるのかと言われるとまだまだ疑問符ではありますが、良くSFなどで目にする自動運転車のみになった道路、ただの夢物語というわけではないのかも、ということを否応なしに感じさせます。
.jpg?width=648&height=302&name=Apollo%E3%81%A8Pony%20(1).jpg) 左がApollo、右がPony(筆者撮影)
左がApollo、右がPony(筆者撮影)

無人車両の様子。本当に勝手にハンドルとペダルが動く。モニターには周囲状況が(筆者撮影)
こういった技術は中国メーカーの高級車ラインにはすでに一定レベル組み込まれており、今後は安価モデルにも導入していくというメーカーも出てきています。もちろん法令等の規制によって、レベル3相当の性能であっても現在はメーカーとして公式に「アイズオフ」運転できると言うことはできません(俗にレベル2+とか、2.9と言われている模様)が、北京では法整備によって今年の4月以降にレベル3の運転が解禁されるという情報も出ていますし、2026年には中国国内でレベル3が100万台、2045年にはレベル3以上が2,500万台を超える、という分析記事もあるため、今後この動きは加速していくと思われます。
しかしながら、やはり現地での自動運転の評判を聞いていると、タクシーは渋滞の原因になるだとか、人間の操作ミスと組み合わさることで逆に事故の原因になる、といったまだまだ未成熟な部分も残されていそうです。何でもかんでも危ないと言って規制してしまうのは技術革新の阻害要素であるとはいえ、安全と利便性の追求は忘れずに取り組み続けてほしいものです。
②中国メーカーの海外展開
中国企業の海外輸出が著しいのは本文で述べた通りです。中国国外に出張や旅行に行った際、街中で中国車を見かけることも大分多くなってきました。
特にヨーロッパや東南アジア、オーストラリア、中東では割合も相応に高くなっており、もし皆さんがそれらの国に行った際には(日本では)見慣れない車種に注目してみると面白いかもしれません。

写真左:オーストラリアで見かけた長城汽車(筆者撮影)
写真右:タイの街中にいたAvetr(長安汽車のプレミアムEVブランド。ドアのところに保護材ついているが納車直後???)(筆者撮影)
またもやあとがきが長くなってしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。


記事投稿者:Shunichiro. F
新卒で銀行に入ったのち、2015年商船三井へ転職。法務に4年在籍後、MOLACEでアジア・大洋州の営業に従事。 2022年の7月にロックダウン明けの中国上海へ降り立ち、目まぐるしく移り変わる中国情勢と日々格闘中。 趣味は旅行で、写真はパラオの天然泥パック入江であるミルキーウェイにダイブしたときのもの。
オススメ記事
2021年03月10日
- エネルギー
2022年06月28日
- 海運全般
2021年04月13日
- 海運全般
2025年04月21日
- 海運全般
2020年09月02日
- 海運全般
最新記事
2025年12月24日
- 海運全般
2025年12月15日
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年12月01日
- 環境負荷低減
- 海運全般