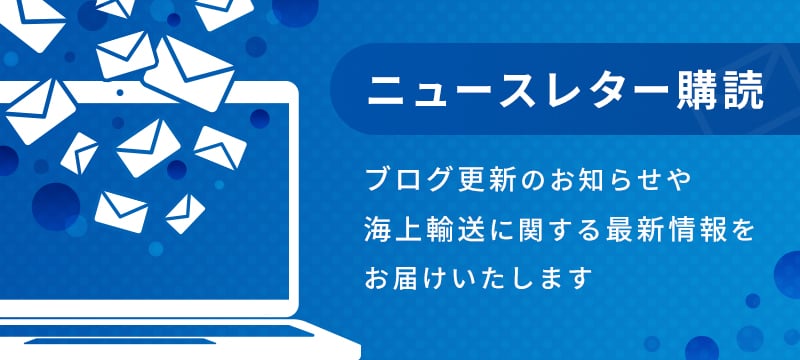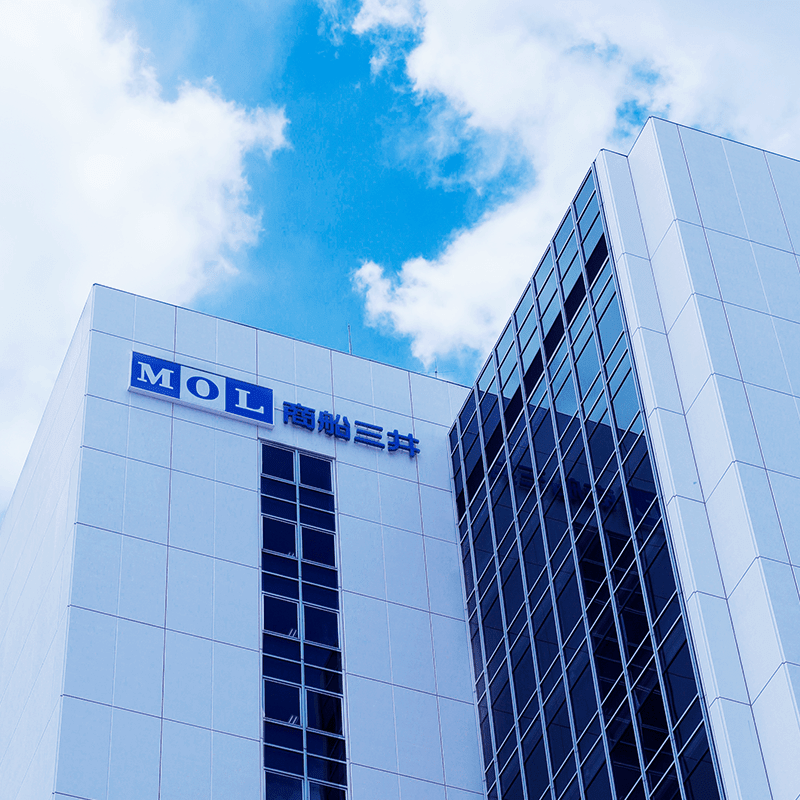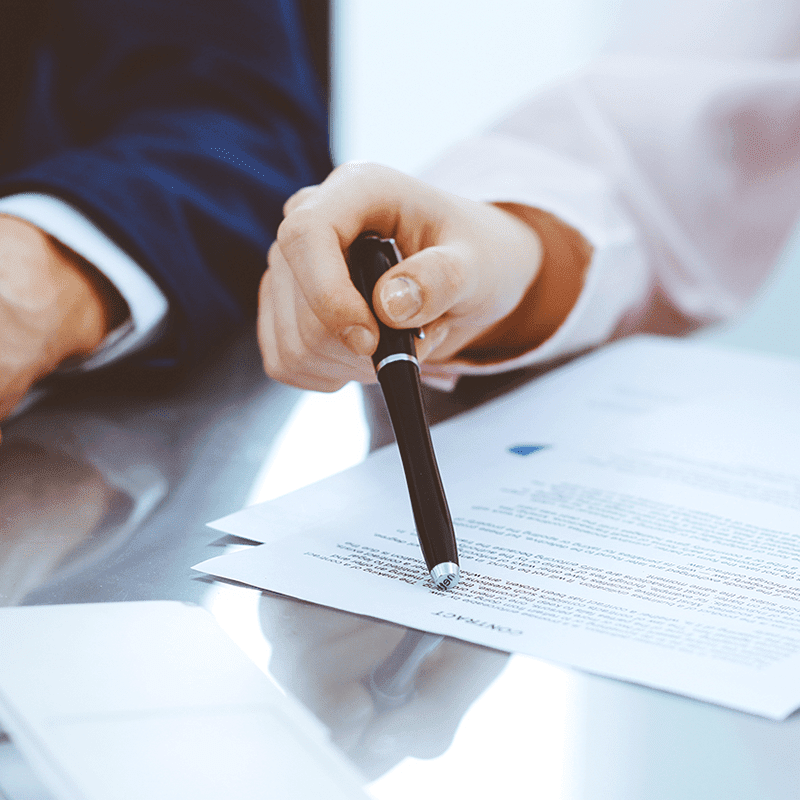BLOG ブログ
「海運×イノベーション」 MOL PLUSがCVCで切り拓く新たな可能性(前編)
- 海運全般
2025年04月04日
100年以上の歴史を持つ海運業界は、「船で貨物を運ぶ」という確立されたビジネスモデルのもと、新規事業が生まれにくい環境にありました。しかし、時代の変化とともに、物流の未来を見据えた新たな挑戦が求められるようになっています。
そうした中、海運業界で初めてのCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)として設立されたのがMOL PLUS(エムオーエル・プラス)です。海運業と社会に新しい価値を「プラス」する組織として2021年に立ち上げられた同社は、どのような変化を遂げてきたのでしょうか。今回は、その立ち上げメンバーであり、代表を務める阪本 拓也氏に、これまでの軌跡と今後の展望についてお話を伺いました。
海運業初のCVCが担う役割とは
--- MOL PLUSについて教えてください。
阪本
MOL PLUSは、商船三井が新規事業を開拓するために設立したCVCです。既存の海運事業にとらわれず、革新的なビジネスを創出することを目指し、スタートアップとの連携を推進しています。
国内外のアーリー・ミドルステージのスタートアップ企業を対象に投資を行い、出資計画枠は40億円。投資の約7〜8割をスタートアップへの直接投資、残りの約2〜3割をVC(ベンチャーキャピタル)ファンドへの出資に充てます。投資先とのM&Aやジョイントベンチャーを通じて、商船三井の利益に貢献し戦略的リターンを得たり、エグジットによる財務的リターンの獲得や人材交流・知見共有などの副次的リターンも狙っています。

MOL PLUSについて詳しくはこちら
【商船三井】過去最高利益、更新。なぜ、今「知の探索」に注力するのか
MOL PLUSサイト
---これまでのCVCのトレンドと比べ、何が変わってきたのでしょうか?
阪本
15年ほど前は、ベンチャーといえばソフトウェア企業が中心。これらのビジネスモデルは比較的資本を必要とせず、優秀なエンジニアがいれば単独で成長できたため、事業会社との連携は必須ではありませんでした。しかし近年では、環境問題や社会課題の解決が重視され、単なる利便性向上ではなく、地球規模での大きな課題に取り組むスタートアップが求められています。そのため、重厚長大な事業会社との協業が不可欠となっているのです。かつてはスタートアップと距離があったプラント業界や重工業の企業も、現在では協業を希望する企業ランキング上位に入っています。
この流れの中で、海運業に対する期待も高まっており、MOL PLUSの立ち上げ時に関係者へヒアリングを行った際も、「商船三井の新規事業開発を歓迎する」という声を多く聞きました。日本の海運業界ではCVCを手がける企業がほとんど存在せず、その希少性から、海運・物流・海洋事業へのアクセスを持つ商船三井は投資家として大きな強みを持っています。例えば、港湾に再生可能エネルギーのソリューションを導入する場合、港湾のオペレーションに関する知見や、世界中の港とのコネクションを持つことは事業の成長に欠かせません。こうしたインフラを活用できる商船三井の存在は、これからのスタートアップにとって非常に価値のある魅力的なパートナーとなるでしょう。

「テーマ」を軸に協業の可能性を探る
---投資先を選ぶ基準として、どのような点に注目していますか?
阪本
投資先の選定において最も重視しているのは、「成長の可能性」と「連携の可能性」です。具体的には、企業が計画通りに売上を拡大し、利益を生み出すかどうか。また、どれだけ商船三井と協業できるポテンシャルを持っているかという意味であり、これらがまず大前提となる基準です。
しかし、それだけでは抽象的過ぎるため、社会課題や成長領域を念頭に「投資テーマ」を設定しています。 例えば「海運業界の人手不足」というテーマであれば、自動化するためのロボティクス領域、業務効率アップのためのデジタル領域など、さまざまな領域が候補にあがってくるわけです。領域ありきで投資先を選ぶのには限界がありますから、そうではなく、テーマで見ていく方法が最も適していると考えています。
追及しているテーマのひとつが「海の利活用における新しいビジネスモデル」です。「海の再生可能エネルギー」であれば、洋上風力発電、波力発電、海洋温度差発電、潮力発電などさまざまなベンチャー事業が生まれています。また人口増加に伴うタンパク質源確保の重要性から、水産養殖は市場規模が拡大しています。漁獲後の輸送という点ではコールドチェーン(低温輸送)も関連し、商船三井との連携が期待できる分野です。ブルーカーボン(海洋を活用したCO₂吸収)への関心も高まり、環境課題の解決に貢献する新規事業が増えています。それから少し変わったところでは、2024年に「将来宇宙輸送システム株式会社」というロケットを開発する企業への投資を決定しました。「宇宙と海に何の関係があるのか?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。ロケットは発射後にすべて宇宙に残るわけではなく、胴体部分は数十回再利用します。回収を行うのは洋上になりますので、発射回数が増えればそこにビジネスチャンスが生まれるというわけです。本当に、海には無限の可能性が広がっています。

現状行っている投資全体で見ると、海運物流系のテーマに関する投資が3割程度、海洋新規事業系が3割程度となっています。残りの4割は、テーマにかかわらず注目している新規ビジネスです。革新的なテクノロジーやビジネスアイデアは私たちだけでは思い付けませんから、テーマに沿うだけではチャンスをとらえきれません。常にアンテナを張り巡らせてマーケットトレンドをキャッチし、候補となる投資先を探しています。
多角的に新規事業創出を目指す
---MOL PLUSは2021年の誕生から現在まで、どのように成長・変化してきましたか?
阪本
投資案件の数は直接投資が24社、VCファンドへの出資が6件と、目標通りに推移。イギリスやシンガポール、インドなど世界中に拠点を構え、18名のメンバーが国境を越えてスタートアップ投資の幅を広げています。また、商船三井グループとしても再生可能エネルギーに特化した「MOL Switch」というファンドを立ち上げたり、不動産関連のダイビルもCVCを開始したりと、グループ全体で新規事業創出を加速させています。ただし、新規事業であるため課題も多く、長期的な視点でのフォローアップが必要です。
---今後、MOL PLUSが成長するために必要なことは何ですか?
阪本
これから求められるのは「メリハリ」ですね。新規事業を成功させるためには多くの投資先を確保する必要がありますが、一方で打席数と打率のバランスも重要です。今後2~3年は、より大きな成果が期待できる上位2割程度の案件を見極め、そこに人材や資金などのリソースを集中的に投入することがポイントになるでしょう。
それに関連して、人材の確保と育成が大きな課題です。MOL PLUSの約半数は商船三井からの社内公募者であり、高いモチベーションをもって参加してくれています。しかし海運業はインフラを担う企業であるために、確実な業務遂行は得意でも、多くの失敗を重ねながらチャレンジし続けることに慣れていないケースも。一方で外部から来たCVCやコンサルなどの出身者は、業界特有の時間軸の長さや、商船三井内の折衝で共感を得やすいコミュニケーション方法などを習得する必要があります。海運物流に関連する分野では経験者を活用し、新規事業分野では外部出身者の専門知識を取り入れるなど、オンボーディングとアサインメントの両方をうまく組み合わせて、適材適所の配置を行っています。新規事業に適した人材を育成し、挑戦し続ける環境を整えるために、MOL PLUSとして主体的に人材育成に取り組み、活躍できるサイクルを作っていきたいですね。

とはいえ、新規事業の成功には、「これがやりたい!」という個々の意欲が欠かせません。トップダウンですべてを決めるのではなく、各自がテーマに合致した領域で最大限の力を発揮できるよう、社内外の関係者とディスカッションしながら役割を決める柔軟な体制を築いています。
---今後の展望をお聞かせください。
阪本
私たちが目指しているのは、新規事業を生み出すことです。その点でいえば、MOL PLUSが行うスタートアップ投資と、社内での新規事業開発はアプローチが異なるものの、目指すゴールは同じ。そのため、商船井三井の各事業部門とも連携を強化し、新規事業開発をサポートしていきたいと考えています。私たちは日々スタートアップの成長の可能性を探求する『目利き』が仕事ですから、「この点が計画として弱いんじゃないか」「もう少し競合他社の分析をしてみたら」などのアドバイスは得意とするところです。自分たちの守備範囲に固執せず、視座を上げて新規事業創出を目指す人たちに伴走していきたいですね。

※本記事は2025年2月に実施されたインタビューを基に作成しています。

記事投稿者:商船三井 コーポレートマーケティング部
オススメ記事
2021年03月10日
- エネルギー
2022年06月28日
- 海運全般
2021年04月13日
- 海運全般
2025年04月21日
- 海運全般
2021年05月14日
- エネルギー
- 環境負荷低減
最新記事
2026年02月10日
- その他
2026年01月26日
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年12月24日
- 海運全般