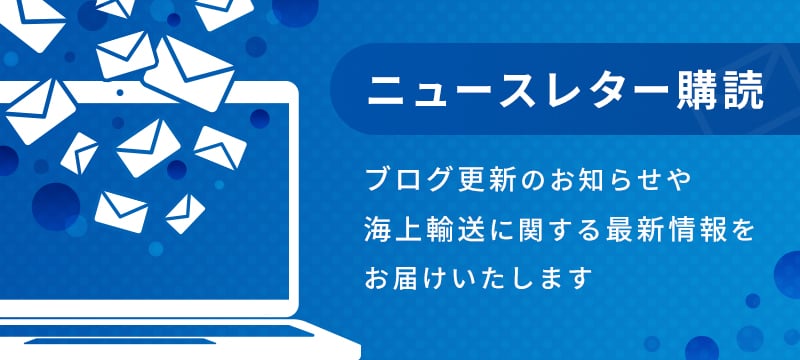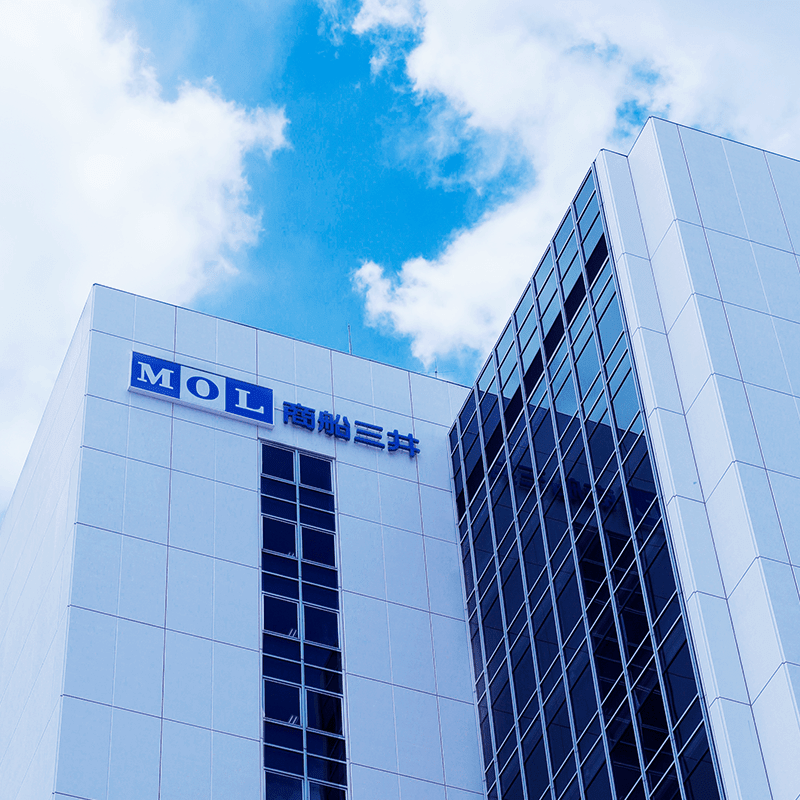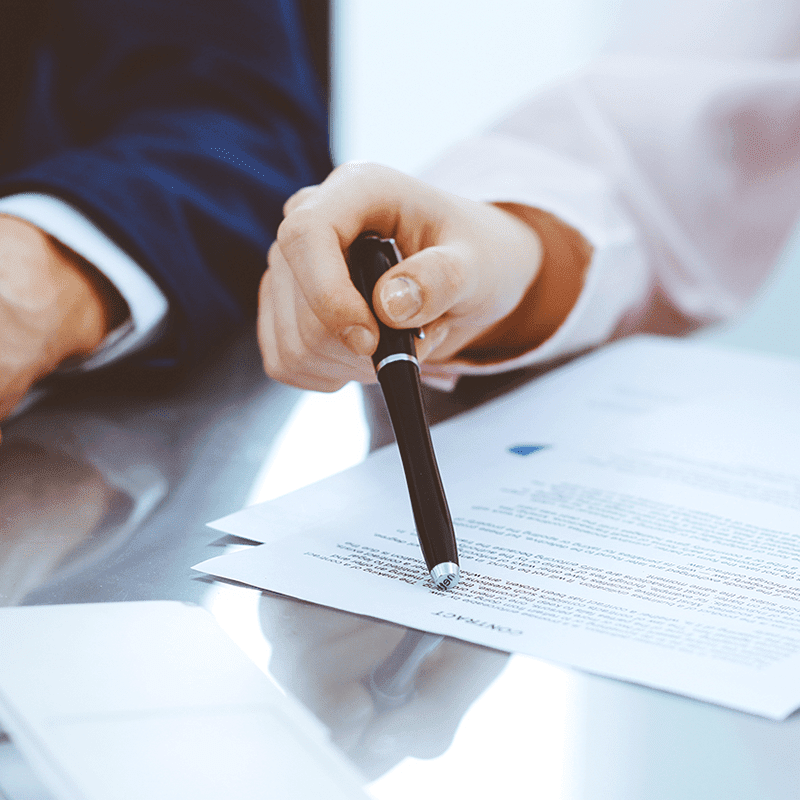BLOG ブログ
DarWINプロジェクトとEcoMOL データドリブンのまったく新しい効率運航手法を構築する
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年01月09日
商船三井は、船舶の新たな効率運航手法の構築を目指す「DarWINプロジェクト」を進めており、徐々にその成果が見え始めてきた。多種多様な船舶の運航データを収集・集約するデータプラットフォームの整備だけでなく、データを解析して効率運航を開発する専門会社EcoMOLの活動が本格化。GHG(温室効果ガス)のゼロ・エミッション達成という目標に向けた運航手法の提案は、海運会社としての事業使命の進化を促している。
ダーウィンの進化論のように自らを進化させる
「DarWINプロジェクト」
商船三井は、「環境ビジョン2.2」で2050年までにGHG(温室効果ガス)ネットゼロ・エミッションの達成を目標とし、そのために具体的に次の5つの領域で取り組みを続けている。
①クリーンエネルギーの導入
②さらなる省エネ技術の導入
③効率オペレーションの推進
④ネットゼロを可能にするビジネスモデルの構築
⑤グループの総力を挙げた低・脱炭素事業の拡大
このうちネットゼロの20%を、②と③の省エネ技術の導入や効率オペレーションの推進で実現させる。

「中長期目標達成のための5つのアクション」の図解
効率オペレーションへの各種の取り組みの総称を「DarWINプロジェクト」という。DarWIN(ダーウィン)とは、「Digital Approach to Reduce GHG With Integrated Network」の頭文字を取ったもの。商船三井 環境・サスティナビリティ戦略部の伊藤雄太 は、「このネーミングには、ダーウィンの進化論を参考として商船三井の取り組みが絶え間なく進化し、激変する環境に適応していくという意志を込めています」と話す。
DarWINプロジェクトでは、ハード面では各種の省エネデバイス開発、ソフト面ではより効率的な船舶運航手法の開発が推進されている。両方の取り組みを支え、推進するための前提として各種のデータを集約するプラットフォームの開発が「FOCUSプロジェクト」である。
「FOCUSプロジェクトの進展により、データの収集ツールの高度化が進み、これまで集めきれなかったデータも収集できるようになってきました。そうした事情を反映してDarWINプロジェクトは、効率運航深度化プロジェクトという役割がより明確になってきました」(伊藤)
ちなみに伊藤の所属する環境・サスティナビリティ戦略部は、DarWINプロジェクトの“司令部”のような部署であり、プロジェクトの役割を明確にして対策や計画を立案する。また、関連するメーカーやパートナー企業との連携を図り、実践や実効について確認と評価を行い、営業部門や海技部門らと連携して実行したり、定期的に経営陣へ全社の進捗や成果をレポーティングしたりもする。

「ダーウィンプロジェクト」のロゴと具体的な取り組み
DarWINプロジェクトが始動したのは2021年度の期初からだが、当初は、「2025年度に19年度に比べてマイナス5%の燃費改善」を目標としていた。この目標は、プロジェクト以前からの取り組みの成果もあって23年度末(24年3月期)にはマイナス7.2%を達成。またハード面での投資額や数量、削減されるGHG量などの目標に対しては、23年度下期から2026年度までの3.5年間の計画期間で取り組みが始まったが、半期を終えた23年度末時点で最終目標の2割程度を達成できている。プロジェクトは順風満帆に進んでいるように見えるが、決して気を抜けないという。
「海運業には市況の波があり、経営状況を大きく揺らします。そのためGHG削減への取り組みも、時には悪化する事態も想定されますが、商船三井は、市況に左右されないGHG削減の推進を目標として掲げ、着実に成果を上げられるような取り組み手法を構築しようともしています」(伊藤)
 商船三井 環境・サスティナビリティ戦略部 伊藤雄太
商船三井 環境・サスティナビリティ戦略部 伊藤雄太
タンカー、バラ積み船、自動車運搬船……etc.
約900隻の多様な船から届く膨大なデータを解析
FOCUSプロジェクトによるデータプラットフォームによって、船舶の運航に関わるありとあらゆるデータが収集できるようになってきた。例えば、従来は航行中の船からe-mailで運航管理者に送られていた「日報」も自動収集、データベース化され、そこに記された天候や波の状況と運航距離、燃料消費量などについて相関を多様に分析できるようにもなっている。さらにエンジンや発電機等の本船上にある様々な機器についてセンサーで計測された運転情報がリアルタイムに陸側管理者に届き、共有されている。簡単に言ってしまえば、運航中の船について陸側の管理者が常に状況を把握できるようになり、広大な海の上で船は「独りぼっち」の航海を続けるようなことはなくなったのだ。
商船三井では約900隻の船、それもタンカーやバラ積み船、自動車運搬船など多種多様な船を運航しており、それぞれのデータが収集されている。「となると、次なる課題は、収集されたデータをどのように活かし、自らのアクションの改善に落とし込むかです」(伊藤)。
それはつまり、データサイエンスに基づく、効率運航の新たな手法の開発ということである。商船三井は2022年、そのための専門の会社をフィリピンに設立した。それがEcoMOL社だ。なぜフィリピンにEcoMOLを設立したのか。同社社長である横橋啓一郎によると、日本の海運会社が運航する外航船に乗船する船員は推計で約5.5万人、うち外国人船員はフィリピン人が約75%、その他のアジア人(インド人、中国人、インドネシア人など)が20%となっており、アジア人の船員が9割を占めているという。
実際、商船三井の運航船においても約7割がフィリピン人であり、彼らの海事知識に関するリテラシーは極めて高い。さらに、同国は英語が公用語であるうえに、日本との時差は1時間ほどで商船三井本社とのコミュニケーションが取りやすいという点も大きい。そして国民の平均年齢が24歳と若者が多く、「何をするにも前向き、かつ真摯に取り組む姿勢に惹かれた」と横橋は話す。
多くの船舶から得られた膨大なデータを効率運航に活用する同社だが、一口に、データを解析してアクション化すると言っても、事はそれほど簡単ではない。横橋は、「EcoMOLの使命は、本船から収集したデータをつかえる形に整え、分析・評価を行い、効率運航を推進するための具体的な施策に落とし込む一貫した手法を確立すること」とした上で、次のように説明する。
「具体的には、データ同士の相関を見出し、評価軸をつくり、実績についてまずは徹底的な可視化を行います。その上で改善につながる施策を立案、実行に落とし込み、実際の燃費改善効果を検証するのです。一連の作業を繰り返すことで、有効な施策を絞り込み、他運航へ水平展開、継続的なプロセスにとして運用することを行っています。」(横橋)
.jpg?width=525&height=535&name=Eco%20MOL%20and%20Mr.%20Yokohashi%20(3).jpg)
EcoMOL Inc. 代表取締役社長 横橋 啓一郎
各船の運航の“癖”まで明らかにし、
合理的で効率的な運航手法を提案する
では、どのような効率運航のマネジメント手法が創造されようとしているのだろうか。
例えば燃費について。自動車であれば、坂道でアクセルを踏み込めばそれだけ燃料を消費する。船の場合は坂道が波の状況に変わる。海面のうねりや風が強ければそれだけエンジンの回転数を上げなければスピードは落ちてしまう。スピードを2倍にするには約8倍の燃料が必要となるが、逆にスピードを下げると燃料消費は格段に減る。EcoMOLでは、一航海当たりの海上の状況と燃料消費の状況をレビューして運航を担う担当者に分析結果を共有、各船の運航特徴の把握や、今後の航海での改善できる点を相互に話し合い、改善につなげている。
また、本船の詳細な性能分析と精度の高い気象予測を組わせて、状況に応じたその時々の「最適な回転数」を導き出し、頻度高く船に最適な推奨回転数を提示、本船船長の意思決定を支援している。
「海運会社の使命は、お客様の荷物を目的地に安全かつタイムリーに届けることにあります。そのために船長以下の航行担当者には、当然、荷物を届ける所定の期日に遅れたくないという責任感による心理が強く働きます。その結果として、予定よりも数日早く目的地に着くこともあります。期日よりも早く到着して良かったという見方がある一方で、効率運航の観点からするとそれは必ずしも合理的な判断と言えない場合もあります。気象状況などとも組み合わせて考えれば、実はもっと省エネかつ経営効果も高い運航ができたのではないだろうか。私たちEcoMOLは、そう考えるのです」(横橋)
 荷物を積み航行する商船三井の船
荷物を積み航行する商船三井の船
船の運航において、最終的な責任者は船長である。いくら効率的な運航のデータ分析や手法をフィードバックしても、それを実際の運航に採用するかどうかは船長の判断次第なのだ。ここからは笑い話になるが、フィードバックを採り入れない船長の運航でも、当然ながらそれはそれとして何度も分析され、フィードバックされる。その結果を船長がどう見るか。こうした作業も効率運航には重要な作業の一つになるのだという。
横橋は、「効率運航においては、『これさえやればすべての問題が解決する』といった飛び道具的な施策はありません。野球で言えばバントやシングルヒットを積み重ねて着実に得点へとつなげていくようなもの。そうした地道な活動がゼロエミッションを実現していくのだと考えています」と語る。
「新しいことはリスク」というジレンマをどう超えるか
先に、フィードバックされた解析データを採り入れるかどうかは船長次第だと紹介した。伊藤によれば、約900隻もの多様な船種から収集されたデータによって、効率運航について約900の対策項目が抽出されているという。だが、効率運航のための手法開発が進み、現場にフィードバックされても、日々の業務の推進は現場の権限である。
「『これは現場で決められないので』とマネジメント層を巻き込んだり、『これはよくわからない』という質問をもらってこちらとキャッチボールができるような状況が生まれたりすることは、私たちにとって喜ばしいことです。というのも、現場によってリテラシーは違い、意欲にも差があるので、そうした機会を通じて理解を深めてもらうことができるのです。環境対策の推進は私たちの使命。しかし、具体的な対策を現場へ浸透させていくには一工夫も二工夫も必要です」(伊藤)
こうしたことの背景には「安全運航」を第一とする考えも影響している。世界最高水準の安全品質を掲げる商船三井にとって見方によれば「新しいこと=実績が乏しいこと」であり、それはリスクでもあるのだ。海の上では万が一のことが起きても、助けはすぐには来ない。だからこそ現場では慎重な判断が求められ、ゼロエミッションを目指したさまざま試みは高い安全品質を確保したうえで実現していく難しさがある。ただ、改善のための糊代ならぬ「やり代」が多くあるのも事実であり、これは経営陣から現場まで一丸となり議論や意思決定をして実行していかねばならない。

安全ビジョンの全体像
こうした課題や難しさを打ち破るには、「従来の部門別の取り組みではなく、全社的に横串をさした一貫した取り組みとし、効果を可視化し、かつ高い粒度で確認できる仕組みが必要だと考えています。そのために造船メーカーなどにも協力を仰ぎ、投資効果や効果的な業務のための意志決定の方法なども示して“現場の雲が晴れる”ような状況づくりに力を注いでいます」と、伊藤は話す。
ちなみにEcoMOLを率いている横橋は、就任前は伊藤と同じ部署にいてDarWINプロジェクトの立ち上げを共にしてきた。そのため現場導入のジレンマもよく理解できるという。
「各種の対策は、確実にできるものばかりでなく、導入に時間がかかっているケースも少なくありません。投資は各部門の責任で行われますので、想定した効果が出なければ、私たちの提案への批判も出るでしょう。しかし、私は一歩だけ踏み込んで現場に新しいアイデアを打ち出し、現場のマインドセットに刺激を与えることが不可欠だと思っています。そうしなければ、変化も、進化もできないのです」(横橋)
人は、今ある状況を変えることを怖れるものだ。しかし、変えていかなければ自らの使命を自らが否定する事態を招く。例えば船の燃料は重油からLNG、アンモニア、水素、メタノールなどの活用へと変わろうとしている。しかし新燃料の価格は現段階では非常に高く、効率運航などの新手法を構築しなければ、その燃料コストはそのまま顧客に転嫁されてしまう。商船三井は、こういう事態を事業使命の否定だと考える。
自らが変わり、そのノウハウを世の中に広げれば世界は劇的に姿を変える。それがDarWINプロジェクトの進化そのものなのである。

写真左 商船三井 環境・サスティナビリティ戦略部 伊藤
写真右 EcoMOL Inc. 代表取締役社長 横橋(左)と現地スタッフ(右)
※本記事は2024年7月に実施されたインタビューを基に作成しています。

船上データ分析統合基盤 FOCUS
FOCUSは船上データの力で船の安全、環境、商流を強化する為の新たなスタンダードを創造し、次世代の海運Digital Transformation(DX)を実現します。
オススメ記事
2021年03月10日
- エネルギー
2022年06月28日
- 海運全般
2021年04月13日
- 海運全般
2025年04月21日
- 海運全般
2021年05月14日
- エネルギー
- 環境負荷低減
最新記事
2026年02月10日
- その他
2026年01月26日
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年12月24日
- 海運全般