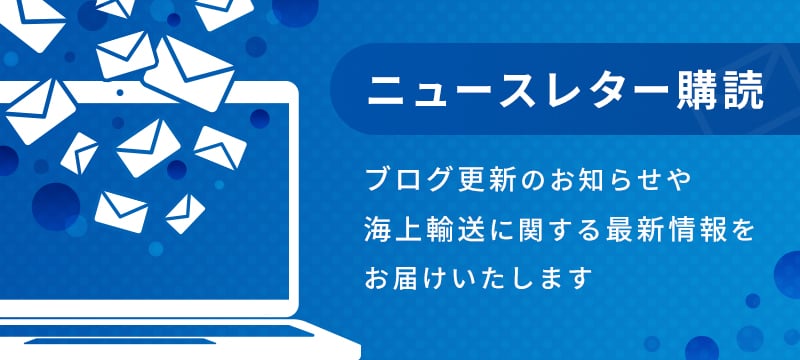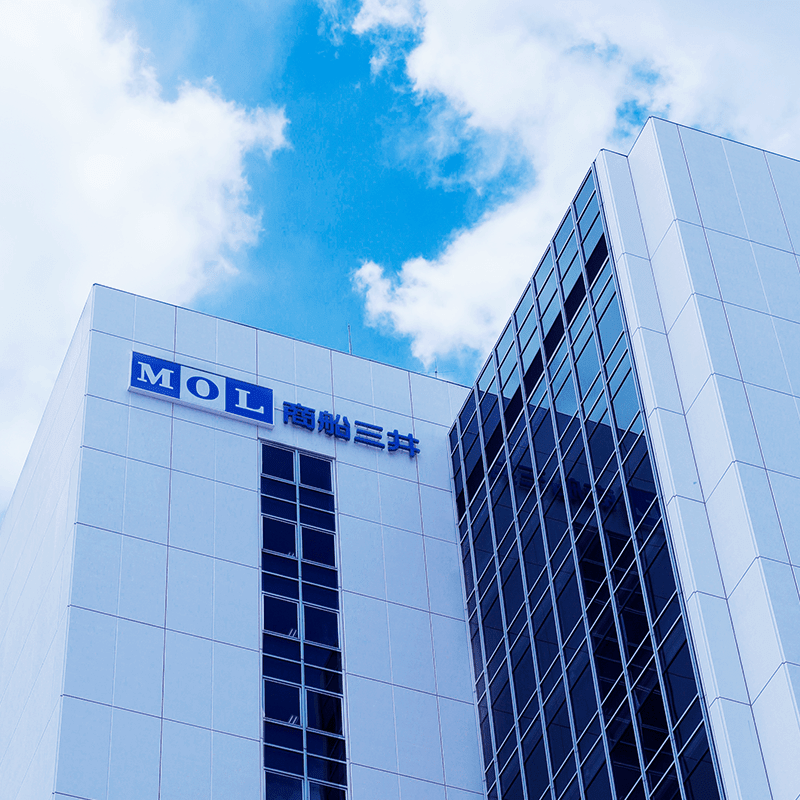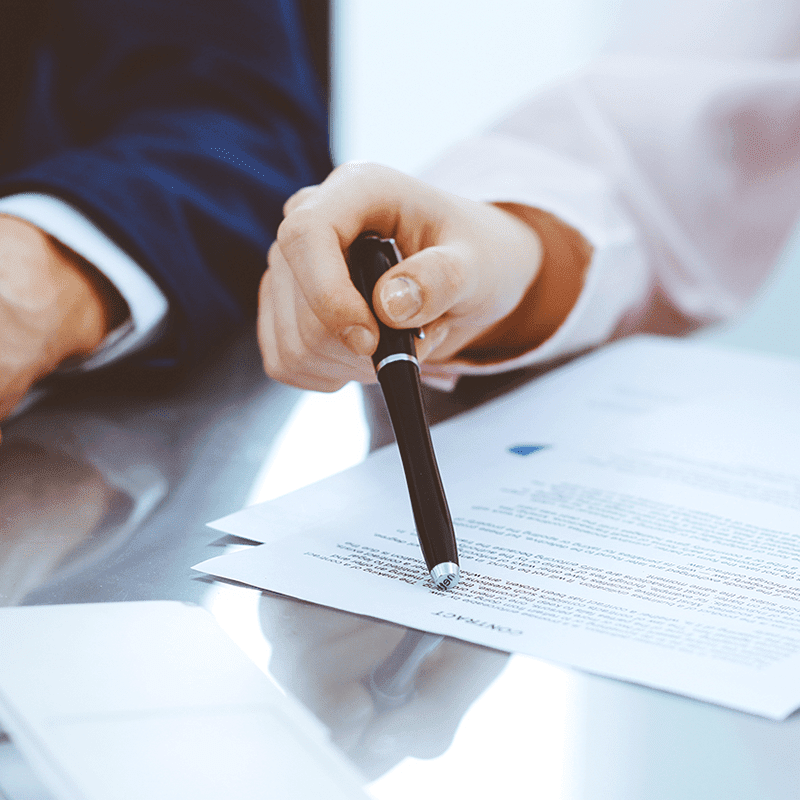BLOG ブログ
トルコ駐在8年の発見:海事産業の活況について(商船三井)
- 海運全般
2025年03月11日
2017年2月にトルコで駐在を始めて、約8年、トルコに駐在しました。社歴は長いのですが、これまでトルコ関係の仕事はしたことがなく、初めてトルコと関わることになりましたが、トルコで海事産業がここまで活況であるとは、全く知りませんでした。このようなトルコの海事産業の状況を、今回はご紹介したいと思います。
(コーポレートマーケティング部 片田 聡)
造船
トルコは黒海、地中海、エーゲ海、マルマラ海と、三方を海に囲まれ、アジアとヨーロッパを跨る長い歴史を有し、西洋と東洋が交錯する地域の大国と言えます。昔から交易の重要な地点にあり、海事産業も発展にも大きな影響を与えています。
トルコでの造船は600年の歴史があります。最初の造船所は1390年、オスマン帝国統治時代のダーダネラス海峡にあるゲリボルに設立されました。1455年、東ローマ帝国を滅ぼしたメフメト2世により、現在もまだ使用されている石造りのドックが残るイスタンブール・ハリチ(金閣湾)造船所が造られました。


金閣湾造船所の昔の様子

金閣湾造船所の現在。現在もフェリーの修繕などが行われている。写真の小型船はイスタンブル市が運用している海上タクシーで、金閣湾造船所で建造されている(出典:İhlas Haber Ajansı)
16世紀までに、トルコの造船所は世界最大規模だった様です。1923年のトルコ共和国の建国後も、造船業の重要性は変わらず、造船所は主にボスポラス海峡と金角湾周辺に位置していましたが、1969年以降はイスタンブル近郊のTuzla(トゥズラ)に移転されました。その後も造船業も順調な発展を続けてきました。

Tuzla地区全景。約43の造船所が稼働している。トルコ海事産業の拠点と言っても過言ではない
(出典:Deniz Harber)
また、2000年代初頭の海運バブル時に、大型船の建造などで建造能力の確保が難しくなっていた小型タンカーなどの建造を行うために、トルコの船舶の最大の輸出先であるノルウェーの船級協会DNVの後押しもあり、Tuzlaのマルマラ海を挟んだ向かいのYalova地区に新たな造船所集積エリアの開発を進めました。しかし、Yalova地区が稼働する頃には、海運バブルは弾けて、新造船が激減し、1隻も作らず撤退した造船所もあった様です。
それ以降、新造ではなく、修繕に力を入れる造船所が増え、老舗のBeskitas造船の様にほぼ修繕の専業となった造船所もあります。また、海運不況時に、これらの造船所を支えたのが、当社も合弁を組んでいるKaradeniz社が開始した発電船事業に使う中古船の発電船への改良で、多くの造船所が、このプロジェクトに参画し、困難な時期を乗り越えました。
Yalova地区全景。ここには30の造船所が稼働している。
手前に見える、船上に煙突の様なものが多数並んでいるのが、当社の合弁相手であるKaradeniz社のケープサイズのばら積み船から改装された発電船である(出典:Milliyet)
トルコの新造船の建造量は、2022年時点で年間17隻と最盛期の約10分の1になっているものの、世界の船腹量の拡大もあり、修繕・定検を主業とする造船所が増え、再び発展を遂げています。2003年に37の造船所が稼働していましたが、2022年時点では、84の造船所が稼働しており、修繕能力も、2013年15.7百万DWTから2022年35.2百万DWTと倍増しました。



(出典:MARITIME SECTOR REPORT İstanbul 2023)
実績のグラフでもわかる通り、トルコで修繕・定期点検を行った隻数が2021年以降に大幅に拡大していることが分かります。この頃と言えば、まだ記憶に新しいですが、新型コロナウイルス(COVID-19)が世界で猛威を振るった頃です。修繕でよく起用されている造船所がある中国やシンガポールなどでは、厳しい入国制限が行われていたため、乗組員の交代、監督の派遣が困難になっていました。しかし、トルコは、外貨準備高も激減し、厳しい状況にあったため、経済を止めることはできず、かなり大胆な開放的な政策をとっていました。例えば、国民はステイホームでしたが、観光客は外出可能であったり、発熱していても入国できたりしました。
このような感じでしたので、他国で問題となっていた入国での制限が少なく、また、造船所で働く作業員は全てトルコ国民なので、人員不足についても問題は起きませんでした。また、COVID-19前に開業した新イスタンブル空港の能力が世界でもトップクラスであり、同空港をハブとするトルコ航空は、エミレーツ航空を抜き、世界最大の空路網を持つ航空会社となっており、世界中からのアクセスが容易な空港となりました。更に加えて、大幅な通貨安により、トルコの造船所の競争力が高まったことも発展の後押しになりました。今回のCOVID-19によって、トルコの造船業は飛躍を遂げたと言っても過言ではありません。
舶用品・周辺産業
このように造船業が発展すると海事の周辺産業も同じように発展を遂げています。技術的に低中級の製品の発展が進んでいます。舶用鋼板・構造部材、プロペラ、航行・通信機器、スラスターなどのハイテク製品はまだ輸入に依存していますが、バルブ・パイプ・チェーン・アンカー・グラブなどの鉄鋼加工品、発電機、ボイラーや圧縮機、甲板・荷役機器、電線、救命艇、ドア・窓などの内装材などが多くを製造・供給できる企業が増えています。約2,200社が出展する世界最大の海事展覧会であるSMM Hamburg 2024では、約90社のトルコ企業が参加しており、うち50社が舶用品製造関係企業でした。
また、最大の船舶保有国であるギリシャを隣国に持ち、造船所などの海事産業が充実するトルコは補完関係にあるようです。船員を手配したり、運航に必要なすべてを取り仕切る船舶管理事業を行うトルコ企業が増えており、国際的な船舶管理会社がイスタンブルにオフィスを構える例も増えています。昔は、船主であったトルコ企業が、船舶管理に専念する例も見かけます。
そのような船舶管理に関わる事業を行う海事系の会社、例えば、船に食料や備品などを調達供給するシップチャンドラー、修理・メンテナンスを行う会社、船員向けソフトウェアの開発・供給を行う会社、船員学校などの教育関係など増えています。
最近の造船動向
トルコの造船所は、検査や修繕に舵を切ったとの話をしていますが、元々、輸出先の殆どがノルウェーなどの欧州であることから、環境面で最新鋭の船の建造が増えています。最近は、洋上風力発電の支援船、5万トンクラスまでのクルーズ船、砕氷船、漁船、活魚運搬船、獲った水産物を船内で加工する設備を備えた洋上加工船、タグボートなどで、LNG 燃料炊きや電気推進の最新の船舶の建造も行っています。一部の分野では、日本の造船所でも作れていないような船も作っています。

電動・LNGハイブリッド客船Havila Pollux(122mx22m)(出典:Tersan造船)

Veidnesハイブリッド・活魚輸送船。LNGを主燃料とする漁業関係の船が多く建造されている
(出典:Sefine造船)

世界初の電動タグもトルコ製。今年、世界初のメタノール電池のタグもトルコのUZMAR社で建造される
(出典:Corvus Energy)
ヨット製造
また、トルコは、大型ヨットの建造でも世界トップクラスで、以前は欧州諸国に次ぐ第3、4位であったが、昨今受注を増やしています。2024年は、オランダを上回り、大型ヨットの50%を生産するイタリアに次ぐ世界第2位の大型ヨット建造国となったようで、2024年132隻(5,838m、約7.3万トン)の大型ヨットを受注しています(Boat International 2023年11月26日記事より)。
 (出典:Boat International)
(出典:Boat International)
ヨットや、当社も支援している海上ゴミ回収船などの小型船舶関連の業界団体であるYATEDのメンバー数は300社を超えています。
シップ・リサイクル
老齢船の解撤について、2023年6月新たな動きがありました。2009年に解撤ヤードにおける労働安全の確保と有害物質の適正な処理処分を確保することを目的として香港でのIMO会議で採択されたシップリサイクル条約(正式名称:”Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009”「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約(略称シップリサイクル条約)」)が2025年6月26日に発効することが確定となりました。
条約の発効要件は、以下の3つ。
① 15カ国以上の締結
② 締結国の船腹量の合計が世界の船腹量の40%以上
③ 直近10年間の年間最大解撤量が締約国の船腹量の3%以上
2021年時点で①はクリアしており、条約発効の鍵を握っていたのは世界最大の解撤国であるバングラデシュでした。
大型船におけるライフサイクルとは~シップリサイクルの現状(前編・後編)はこちら
バングラデシュは2023年までの批准を目指し、国際機関や各国政府とも連携し取り組みを進め、2023年6月にバングラデシュが条約を締結。さらに同日付で便宜置籍船を多数保有するリベリアが条約を締結したことにより、条約の発効要件を充足することとなりました。
トルコは、造船の分野では目立った存在ではありませんが、トルコは世界第4位のシップリサイクル産業を持ち、製鉄でも世界第8位の生産規模で、電炉比率が高く、世界最大の鉄スクラップ輸入国です。トルコ西南部のイズミル近郊のAliaga(アリアー)で22の事業者が船舶解撤を行っています。解撤と言えば、干満を利用して砂浜に船を乗り上げ、人間が手で船を解体して行くイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。作業は汚染や危険が伴うものですが、トルコは相対的にしっかりとした施設での解撤が多く、対岸に海水浴場もあるくらいです。解撤で圧倒的なシェアを持つインドやバングラデシュに比べると賃金・施設の良さなどもあり、残念ながら、コスト面での優位性がなく、解撤船(リサイクル鋼原料)の引取り価格は、インド・バングラデシュよりもかなり安く、解撤数量で両国にはおよびませんが、地中海・欧州・大西洋で活躍する船や欧州船籍などは、多くがトルコでの解撤が行われています。COVID-19の流行期間中、不稼働となった客船が大量にリサイクルに来たことで、トルコのシップリサイクルヤードに脚光が当たりました。
退役に近い年齢の船を運航している船主・海運会社には、相対的に規模が大きくなく、高く買ってもらえるなら、経済性を重視したシップリサイクルを優先することが多いのではないでしょうか。シップリサイクル直前に、規制回避のために船籍を切り替えて、経済性を優先したシップリサイクルするということもよく耳にします。
荒海を航海する船は、巨大で、極めて頑丈に作られており、車のスクラップのようにはいきません。その船の解体には、多くの労働力が必要となり、危険が伴う厳しい環境の下で行われています。また、海岸などで行うため、残油をはじめとするさまざまな有害物質の流出など、環境面でも問題となることも多い産業です。その中で、トルコの解撤業者は、相対的にしっかりとやっているリサイクルヤードの比率が高いと思います。もちろん、作業中の事故もあるし、粉塵などの問題もあるでしょう。しかしながら、労働力が減ってきている先進国では、これらの事業を行うことは難しいかもしれませんが、2000年代に大量に竣工した船舶の引退が今後始まります。先進国が作成するレポートを読むと、トルコのシップリサイクルヤードですら、廃棄物処理、労働環境や条件、シップリサイクル業の解撤処理能力やトレーニングが不足している等、様々な課題を指摘しています。EUが基準を設定し、認証などを与えていますが、多くの船舶解撤業者は、財務基盤も強くない中小企業であり、トルコの場合は全て国内企業です。リサイクル鋼の価格はの価格は流動的であり、マーケットが悪化すると仕入れ価格より安い売値を強いられ、赤字となるケースもありますし、海運市況次第で、解撤される船の数量は大きく変わります。また、受注には、厳しいハードルのあるEU認証、シップリサイクル条約への適合が強いられています。

2020年10月、解撤中の客船(出典:ロイター)
写真上 解撤中の船(2021年筆者撮影)
写真下 21年と比べて、陸側に多くのスクラップが置かれていることがわかる。これはスクラップの引取価格が低いので、価格が上がるまで、できる限り在庫しているもの(2024年筆者撮影)
スクラップヤードを出た道沿いには船からの大小のリサイクル品を売る店が並ぶ(筆者撮影)

世界の新造船建造量の推移、2000年台に建造量が大幅に増えている
(出典:IHS Markit資料より経済産業省作成)
最後に
あまり知られていないトルコの海事産業を駆け足で紹介して来ました。2024年4月に開催されたSea Japanでは、日本とトルコの海事産業の交流促進、多くの日本の船主や海事関の皆様にもトルコの状況を知って欲しいと思い、当社でトルコ・パビリオンを企画しました。最終的に8社のトルコ企業に参加頂きました。

Sea Japanでのトルコ・パビリオン(筆者撮影)
日本とトルコの関係は、1890 年(明治 23 年)に、和歌山県串本町沖で発生したトルコ海軍の軍艦エルトゥールル号遭難事件に遡ります。
その後、イラン・イラク戦争時のトルコ航空機によるイランからの日本人救出や、地震国である両国での相互支援活動など、両国の友好関係の基盤は深いものがあります。一昨年はトルコ共和国建国100年、昨年は日本トルコ国交100周年、そして今年はエルトゥールル号遭難から135周年を迎えます。
 写真左 トルコ軍艦遭難慰霊碑(出典:串本町ホームページ)
写真左 トルコ軍艦遭難慰霊碑(出典:串本町ホームページ)
写真右 エルトゥールル号遭難事件を扱った映画(出典:日本トルコ合作映画 海難1890)
また、トルコの船主の数も減ってきていた為、国際的には余り目立たない存在でしたが、最近、トルコの船主による日本の造船所での新造船の発注などのニュースも耳にするなど、トルコの海事産業が新たな次元に進んでいる様に感じます。
海が繋ぐ日本とトルコの関係に、これからも海事分野での交流を続けて行く必要があると思います。これからも、大きな一歩ではありませんが、当社としても、このような交流を促進していく様に努力を続けて行きたいと思います。
.jpg?width=580&height=545&name=Expomaritt%20Exposhipping%20Istanbul%202025%20(1).jpg) 2025年2月のイスタンブル訪問時に開催されていたExpomaritt Exposhipping Istanbul 2025(2/18-21)。200社を超える、主にトルコの海事関係企業が出展を行い、1万人近い訪問者があった。参加者も主にトルコの方ながら、トルコの海事産業の様子や規模を知るには良い展示会であった(筆者撮影)
2025年2月のイスタンブル訪問時に開催されていたExpomaritt Exposhipping Istanbul 2025(2/18-21)。200社を超える、主にトルコの海事関係企業が出展を行い、1万人近い訪問者があった。参加者も主にトルコの方ながら、トルコの海事産業の様子や規模を知るには良い展示会であった(筆者撮影)
.jpg?width=580&height=744&name=Bosporus%20Boat%20Show%20(1).jpg)
同じ会場で開催されたBosporus Boat Show(屋内)。200社以上の船舶建造者、部品メーカーなどが参加し、300隻以上の船舶が建造されていた。船舶建造者の大半は、トルコのメーカーとのこと。小型船の船外機では、日本メーカーのプレゼンスが高かった。また、毎年秋には、マリーナーで開催されるBosporus Boat Show(屋外)があり、世界から500ブランド、300隻以上の船が展示される(筆者撮影)

世界で活躍する商船三井「トルコ編」~「引っ込み思案」という言葉が辞書にない国の企業との理想的パートナーシップ~
オススメ記事
2021年03月10日
- エネルギー
2022年06月28日
- 海運全般
2021年04月13日
- 海運全般
2025年04月21日
- 海運全般
2020年09月02日
- 海運全般
最新記事
2026年01月26日
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年12月24日
- 海運全般
2025年12月15日
- 環境負荷低減
- 海運全般



.jpg?width=580&height=635&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%80%81%E8%88%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E5%87%BA%E3%81%9F%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E5%93%81%E3%81%AE%E7%BD%AE%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%9F%E9%A2%A8%E6%99%AF%20(1).jpg)