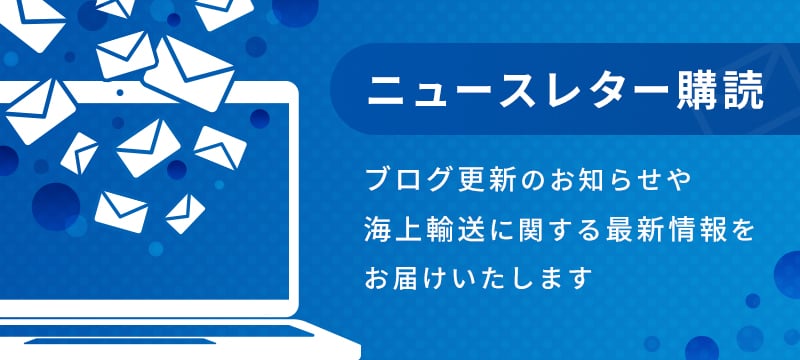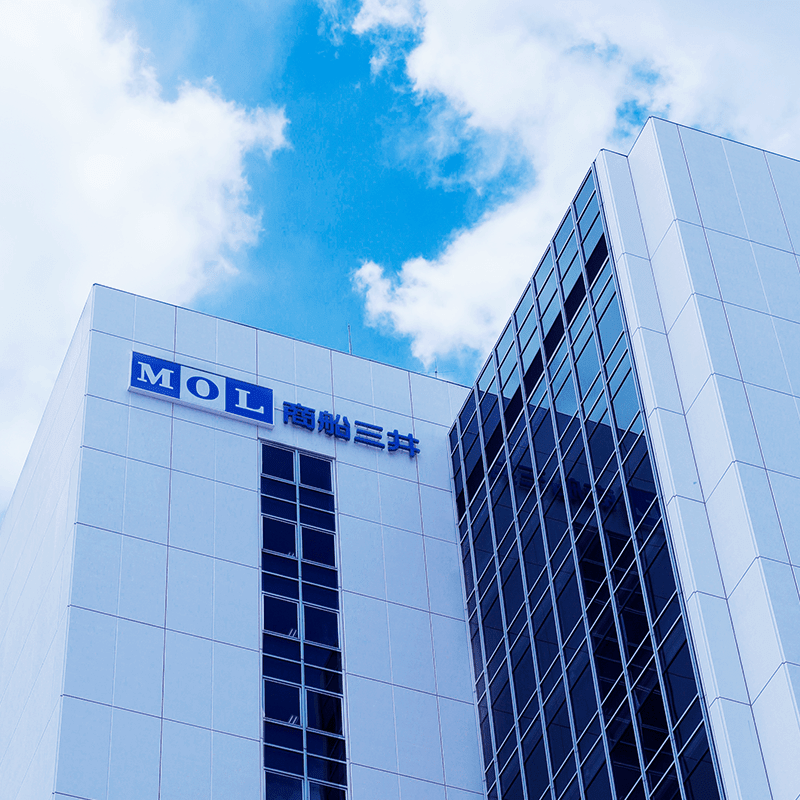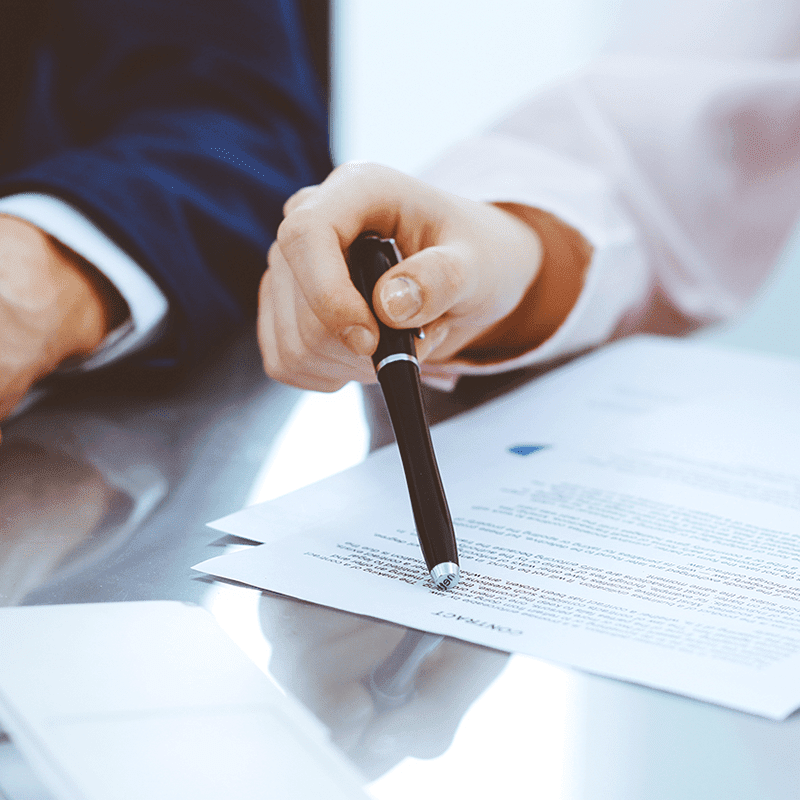BLOG ブログ
6条合意とカーボンクレジット市場 ~COP29 パリ協定締結後9年越しの合意~(前編)
- 海運全般
2025年03月24日
2024年11月、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29*1は資金COPといわれるほど、先進国から途上国への資金支援の具体的額について話し合われることが中心課題でした。しかもCOP開催中にパリ協定からの離脱を訴えていた米国トランプ元大統領の再選が決定し、資金問題にも大きく影響を与えることとなりました。最終的に年間3000億ドルで合意されましたが、元々の途上国からの要望額である1兆3000億ドルからはかなり乖離しているため、2025年開催のCOP30においても何らかの話し合いがもたれることになりそうです。
この資金問題と並んで注目されていた議題が、パリ協定における最後の未合意条項であった6条の市場メカニズムです。本稿では、COP29で合意された事項に関して、2項(協力的アプローチ)および4項(国連管理型メカニズム)について、これまでの経緯、合意内容、及び今後のカーボンマーケットへの影響などを考察いたします。
(*1)
COPはConference of the Parties の略でUNFCCC(国連気候変動枠組条約)の最高意思決定機関

写真左 COP29本会議場(筆者撮影)
写真右 本会議場 議題終了後(筆者撮影)
キーポイント
-
国連環境計画(UNEP)本部職員として92年リオの地球サミット準備委員会事務局等を歴任。ケンブリッジ大学大学院卒(MPhil)で気候変動政策の専門家、商船三井 首席ストラテジスト 丹本 憲による解説記事
- COP29で、パリ協定の市場メカニズム、第6条の9年越しの合意が実現
- 第6条メカニズムは、経済合理的なGHG削減を促す柔軟性措置として重要
- 協力的アプローチ(6条2項)と国連管理型メカニズム(6条4項)の詳細ルールが固まる
- クレジット信頼性のため、二重計上を防ぐ相当調整とホスト国の政府承認が重要
- 今回の合意で、国際的なカーボンクレジット市場の利用は今後大きく拡大が期待される
柔軟性措置としての市場メカニズム
最初に市場メカニズム導入の必要性についてお話しします。
先進国だけが温室効果ガスの削減義務を負っていた京都議定書時代とは異なり、パリ協定下ではすべての締約国が削減目標(以後NDC)*2を提出することとなっています。しかしパリ協定ではプレッジ&レビューという方法がとられているため、その目標は飽くまで自主的な目標になります。そして国連管理下の第三者によるレビューを通して実績を確認していくことになります。ところが自主的であるために、単なる努力目標的に提出する国や実現可能性が低い目標を掲げる可能性があることも否めない事実です。ここにも200か国近い国を参加させるための制度的限界がありますが、先進国や多排出新興国などには歴史的経緯における国家の責任からも理性と誠実性を持った対応が求められています。
ところで、企業にしても国にしても経済合理性に基づいて削減を実施する場合には、できるだけCO₂の1トン当たり削減コストの低い取り組みから実施していくことになりますが、そのコストは国によって、また企業によって大きな差があります。そこで比較優位の原則*3に基づいて貿易が行われるのと同様にCO₂排出削減コストが比較的安い国・地域においてプロジェクトを実施し、創出された排出削減分の売買移転が行われることにより、個々の国や企業にとっての経済合理性が満たされるとともに経済全体におけるコスト削減に結びつくことになります。この原理を基にして各国の野心をより高め、温室効果ガス(以後GHG)削減を促進しようとする方法が本稿で扱う市場メカニズムの基礎となります。
(*2)
Nationally Determined Contribution の略でパリ協定上の温室効果ガス排出削減目標のこと
(*3)
各国が 自国内で生産性の高い分野に特化・集中し、そこから産出される財やサービスを交換することで、世界の経済厚生が最大化するという考え方
柔軟性措置としての京都メカニズム
京都メカニズムとは、京都議定書上削減義務を負っていた先進国が自助努力だけでは目標達成が困難である場合の柔軟性措置として設立された国連管理型のメカニズムであり、CDM(クリーン開発メカニズム:Clean Development Mechanism)、 JI(共同実施:Joint Implementation)そして国際排出量取引(Emissions Trading) の3本柱からなります。
京都議定書ではその第一約束期間(2008年―2012年)において、1990年を基準年として日本が▲6%、脱退した米国が▲7%、EUが▲8%など先進国だけが削減義務を負わされました。そして日本は第二約束期間(2013年―2020年)への参加は控えることとしました。その理由としては、大量排出国である米国は脱退し、中国やインドは途上国として削減義務を課されておらず、第一約束期間では削減義務を負う国の排出量カバー率は世界全体の排出量の3割以下となっていたことや炭素リーケージ*4の問題などをあげていました。
第二約束期間に入ると、この京都議定書の機能・実効面への疑義が表面化するにしたがって、2020年以降の新たな枠組みについて議論がなされるようになっていきました。そして2015年にパリで開催されたCOP21において2020年以降の枠組としてパリ協定が採択されました。同協定ではすべての締約国が削減目標を持つことになり、その柔軟性措置として京都メカニズムの後継とされたのが6条4項の内容になります。
(*4)
マーケットリーケージとも呼ばれるもので、激しい国際競争にさらされている企業が排出規制の緩い国へ移転してしまうことで、それによりかえって排出量が増えてしまうことがあり得る
JCMと6条2項
日本が京都議定書第二約束期間に参加を控えた理由を挙げましたが、その他日本が得意としていた省エネに関してCDMでは認められづらかった点などもありました。そこで、日本政府はJCM(Joint Crediting Mechanism)(当初はBOCM*5と呼ばれていた)というメカニズムをつくり、日本の優れた技術を途上国などに広めつつ気候変動問題に貢献していくこととしました。これまでに29か国と締結しており、2030年までに1億トンの削減を目標としています(下表参照)。
パリ協定6条2項は協力的アプローチを定めた条項でありますが、JCMでは基本的に2国間で合同委員会を設立して規則やガイドラインなどが決定される方式を採用しているため、6条2項に沿ったガイダンスやルールに従うことにより、本項での運用が可能となります。

(外務省資料を基に筆者作成)
(*5)
Bilateral Offset Credit Mechanismの略
現在、この協力的アプローチを積極的に進めようとしている代表国として日本の他にシンガポール、スイスなどがありますが、他にも韓国、スウェーデン、ノルウェー、オーストラリアなども進めており、今後はホスト国やプロジェクト発掘において競合関係になる可能性も否めません(下表参照)。
%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E5%9B%BD.png?width=797&height=479&name=6%E6%9D%A12%E9%A0%85%20%E5%8D%94%E5%8A%9B%E7%9A%84%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%92%E9%80%B2%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%B8%BB%E3%81%AA%E5%9B%BD(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A5%E5%A4%96)%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E5%9B%BD.png)
(UNEP Article 6 Pipeline を基に筆者作成)
削減量(カーボンクレジット)の利用目的と政府承認*6
後述する6条4項にも共通することですが、2項に基づいて実施されたGHG削減プロジェクトの成果としての削減分をどのような目的に利用するかによって政府の承認が必要になります。下図に掲げましたように、NDCやCORSIA*7などその他国際緩和目的に利用する場合には、政府承認が必要となります。この場合の政府はホスト国になります*8 。そして政府承認が得られた削減量はITMOs (Internationally Transferred Mitigation Outcomes)と呼ばれ、これを国際移転する場合には相当調整*9が必要となります。こうした承認制度により、ダブルカウント問題に対する懸念がかなり解消され、同時にクレジットのインテグリティ(環境十全性)など質に対する信頼性が高まるものとなります。一方、承認がされていない削減分は緩和貢献として上記目的以外に対して利用が可能であり、相当調整の適用外とされます。
(*6)
この具体的内容も今回COP29における重要合意事項の一つであった
(*7)
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation の略で国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキームのこと
(*8)
その他、ホスト国は活動の許可とプロジェクト参加者の承認を、ホスト国以外の参加国はプロジェクト参加者の承認を行う
(*9)
クレジットを獲得する国がクレジットを売却する国とそれぞれの貢献度などによって分ける仕組みで削減量(吸収量)の二重計上を避けるためにとられる措置
6条4項
本項は国連による中央管理型のメカニズム(以後PACM*10)であり、京都議定書における柔軟性措置であった京都メカニズムのCDMの後継として語られることが多いですが、実はJIの後継でもあり、どちらかというと目標を持った国々の間でのプロジェクトという意味ではJIにより近い意味合いを持つものとも言えます*11。つまり国連管理下においてある国(投資国)が他国(ホスト国)でGHG削減(吸収)プロジェクトを実施し、削減(吸収)分を投資国の削減量にカウントできるという仕組みです。そして、6条2項同様にNDCやその他の国際緩和目的への利用に際してはホスト国の承認、そして相当調整が必要になります。現在この4項によって創出された削減分はA6.4ERsと呼ばれていますが、政府承認を得たA6.4ERsは適応への資金支援(SOP: Share of Proceeds)として5%、世界全体の排出削減(OMGE: Overall Mitigation in Global Emissions)への貢献として2%以上差し引かれることになっています*12 。さらにこの2%以上の分につきましても相当調整が求められています。一方、6条2項につきましては、これらについて強く推奨するにとどまっています。

(IGES資料等を基に筆者作成)
(*10)
Paris Agreement Crediting Mechanism の略で、高い十全性を有するクレジット創出メカニズム
(*11)
ただしJIの場合にはホスト先進国の承認があれば第三者認証機関の検証なしにクレジットの移転が可能であった
(*12)
SOP分は資金拠出、OMGE分はITMOsの償却による
JIは相当調整の先駆け
ところで、先に京都議定書においてCDMを実施した場合においては、約束期間中、先進国だけが削減義務を負わされていたために相当調整の必要がなかったことを述べましたが、それでは削減義務を負っていた国でプロジェクトを実施するJIの場合はどうしていたのでしょうか。実は投資国が先進ホスト国でプロジェクトを実施した場合には、ホスト国が有している排出枠(AAU:Assigned Amount Unit*13)で調整をしていたのです。つまりパリ協定の相当調整と同様のことがすでに行われていたのです。
以上のように6条2項による協力的アプローチおよび国連管理型の6条4項PACMによる市場メカニズムを利用することによって締約各国はそれぞれのNDC目標などを目指すことが可能となります*14 。
パリ協定締結から約9年が経ち、ようやく国連主導の下で新たなカーボンクレジット創出メカニズムが始動することとなり、2~3年後にはこれら6条クレジットの利用が大きく拡大していくものと思われます。
 COP29 REDD+*15に関する会合(筆者撮影)
COP29 REDD+*15に関する会合(筆者撮影)
後編では今回ご紹介しました6条2項の協力的アプローチ、そして6条4項によるPACM始動によってカーボンマーケット市場にどのような影響が及ぶかということについて考察してみたいと思います。
(*13)
初期割当量のこと
(*14)
パリ協定のプレッジ&レビューなどより詳細な内容については、こちらをご覧ください
(*15)
Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks の略で、途上国における森林減少および森林劣化からの排出削減、並びに後から付け加えられた森林保全、持続可能な森林管理、森林炭素蓄積の増強を意味する。これらのうち下線部分が+(プラス)の内容にあたる

記事投稿者:丹本 憲
ケンブリッジ大学大学院卒 MPhil (開発学)、元国連環境計画(UNEP)本部プログラムオフィサー、帰国後は政府系、銀行系、証券系各シンクタンク等を経て2022年エネルギー営業戦略部主席ストラテジストとして入社。30年以上気候変動政策に携わらせていただいています。非常に多趣味ですが、とりわけ音楽なしの生活は考えられません。
オススメ記事
2021年03月10日
- エネルギー
2022年06月28日
- 海運全般
2021年04月13日
- 海運全般
2025年04月21日
- 海運全般
2020年09月02日
- 海運全般
最新記事
2026年01月26日
- 環境負荷低減
- 海運全般
2025年12月24日
- 海運全般
2025年12月15日
- 環境負荷低減
- 海運全般